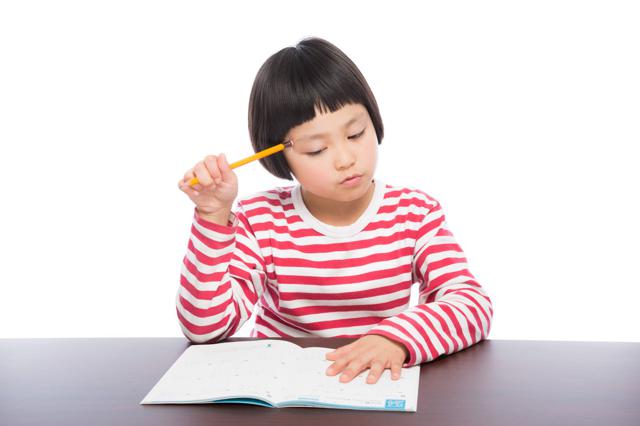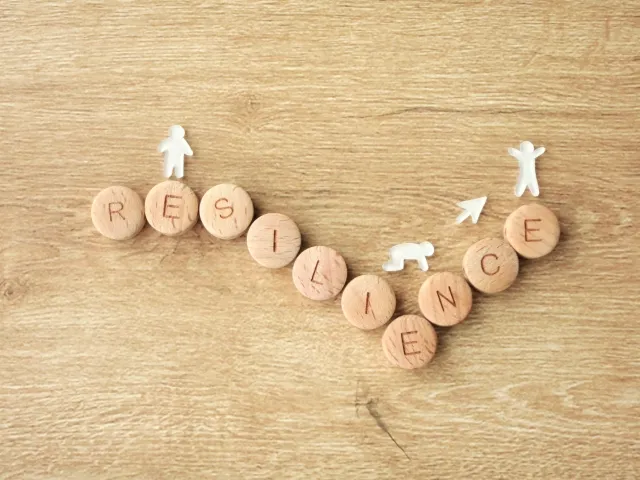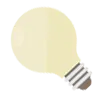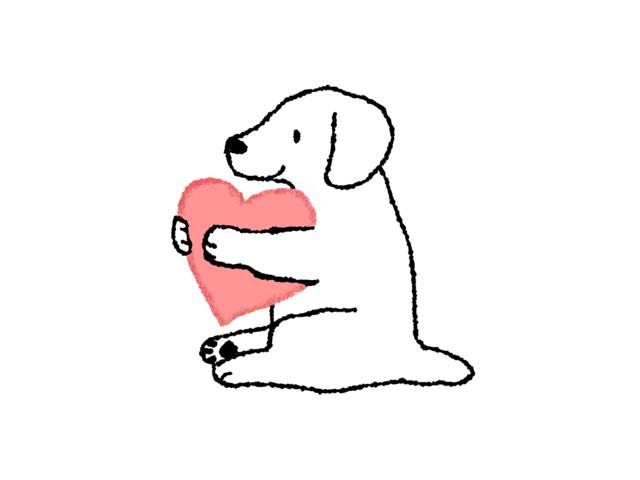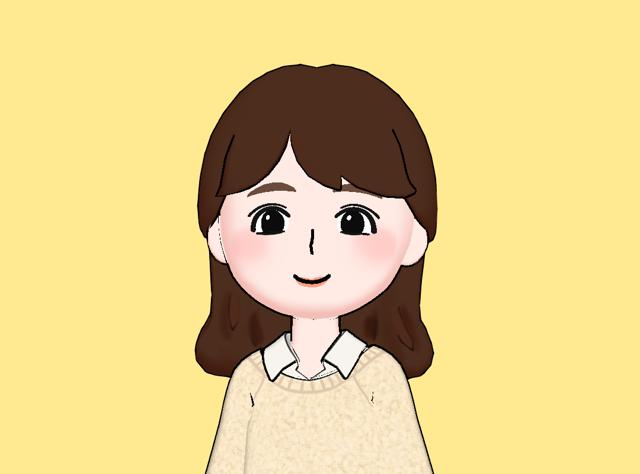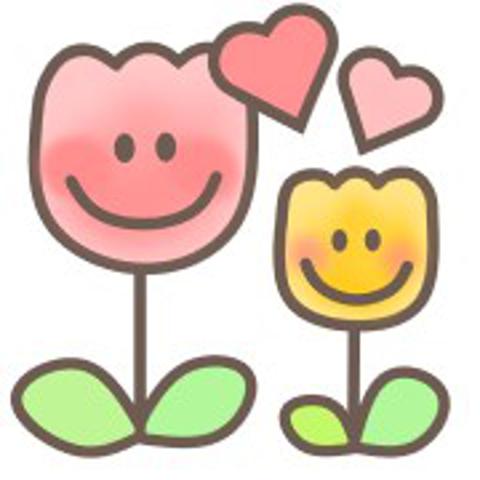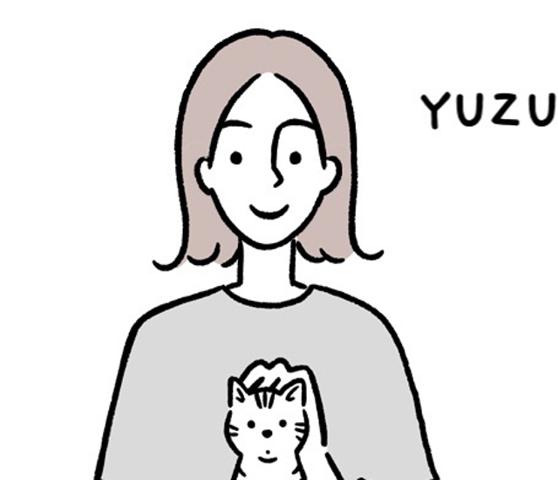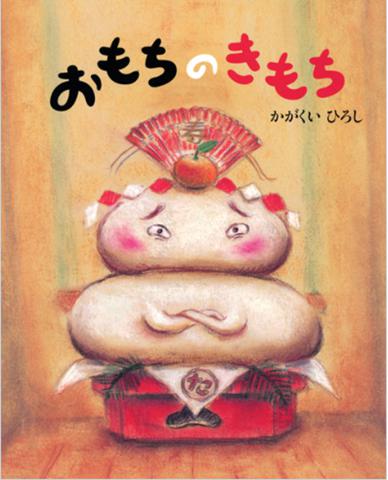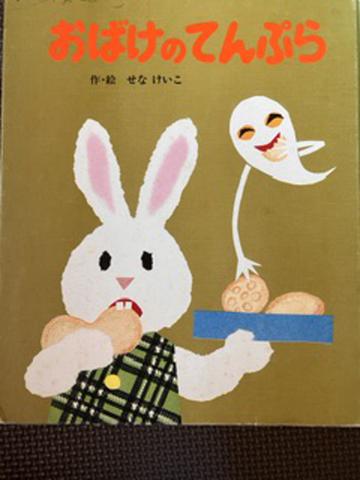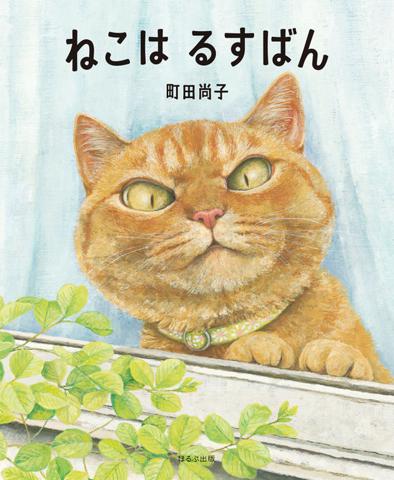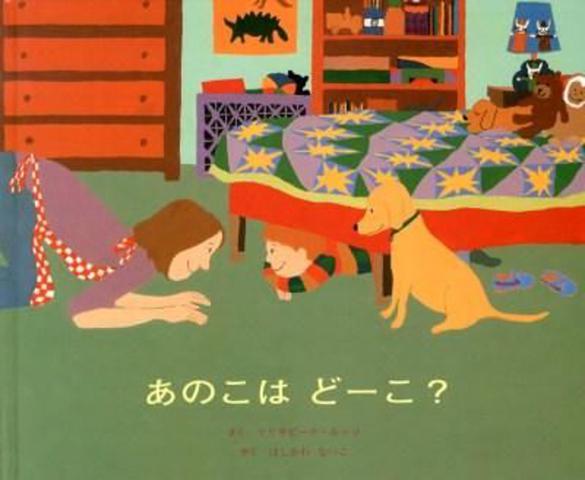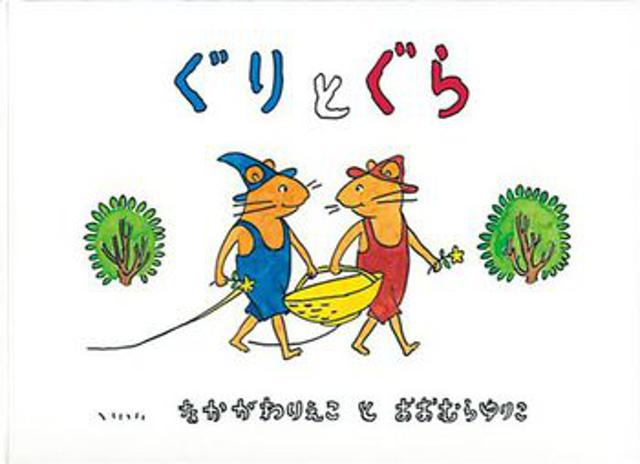| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |
| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |
非認知能力の種類と育て方|子どもも大人も実践できる方法を解説
記事の目次
サマリー
非認知能力とは、IQやテストの点数とは違って数値で表すことができない、自尊心や思いやりといった「心の力」です。これまでの研究からこの非認知能力が社会的な成功や個人の幸福につながる能力であることがわかってきました。今回は、非認知能力の具体的な中身について解説し、それを効果的に鍛える・育てる方法を紹介していきます。
非認知能力には、自尊心や自制心といった「自己にかかわる心の力」と思いやりや協調性といった「社会性にかかわる心の力」があります。そしてこれらの心の力は子どもが不安を感じたときに親や身近な大人に守ってもらう経験を積み重ねることで培われていきます。
スキンシップや「怖かったね」「ここで見守っているよ」という声掛けで、子どもが「自分は愛してもらえる」「人は信じていい」という感覚が持てるように意識してみましょう。
また、大人になってからでも、自分のことを振り返る「内省」を意識することで非認知能力を高めることができます。具体例をあげながら解説していきますので、ぜひ実践してみてください。
記事の執筆者
非認知能力とは?非認知能力の種類や具体的な中身
非認知能力は数値では表せない「心の力」
非認知能力とは、「認知能力以外の心の要素すべて」を表す言葉です。
ここでいう認知能力とは、IQやテストの成績といった数値で表せる能力で、「頭の良さ」のようなものです。
これまではこの「頭の良さ」がその後の進学や収入などの個人の成功や幸福に影響すると言われてきました。
しかし、近年ではこの「頭の良さ」だけではなく、数値で表しにくい「心の力」が個人の成功や幸福に影響する大切な能力として注目され、文部科学省も認知能力と非認知能力をバランスよく育成することが幼児教育における重要事項であるとしています。
非認知能力の種類や具体的な中身は?
非認知能力は認知能力以外の幅広い能力を指しますが、具体的にはどのような能力があるのでしょうか。
非認知能力の具体的な中身について、OECD(経済協力開発機構)は非認知能力を社会情緒的スキルと呼び、次の3つの側面に関する思考や感情、行動のパターンであるとしています。
長期的目標の達成
目標へ向けて、忍耐強く継続して取り組む力
他者との協働
社交性と思いやりを持って他者と協力して物事に取り組む力
感情を管理する能力
自尊心や自信を持ち、自分の感情を理解し対処する力
また、よりシンプルに非認知能力を「自己にかかわる心の力」と「社会性にかかわる心の力」の2つに分けて考えることもできます。
自己にかかわる心の力
自尊心、自己肯定感
自分はありのままで愛される価値があると感じられる力
自己効力感、自信
難しそうなことにも「自分ならできる」と挑戦する力
自制心、自己制御、粘り強さ
誘惑に負けず、自分の気持ちや行動をコントロールする力
好奇心、意欲
興味をもって積極的に物事に取り組む力
社会性にかかわる心の力
心の理解能力
相手の気持ちを考える力
協調性
他の人と協力して物事に取り組む力
共感する力、思いやり
誰かが困っていたら自然にかわいそうと思って助けられる力
社交性、コミュニケーションの力
集団の中で自分の居場所を作り、関係を作る力
道徳性
社会的に何が良くて何が悪いかを判断する力
規範意識
集団の中に存在するルール・決まり・常識などを理解し守る力
非認知能力を鍛える方法・育てる方法

子どもの非認知能力を高める方法
「自分は愛してもらえる」「自分が好き」「人は信じていい」という感覚を持つ
自尊心や思いやりといった非認知能力は、教えられて育まれるものではありません。
親や保育者、教師といった大人と子どもの日常の関係性の中で自然と培われていくものです。ここで重要となるのが「アタッチメント」であるといわれています。
アタッチメントとは、「不安を感じたときに、特定の誰かに身体的に、心理的にくっついて安心しようとする傾向」です。
不安を感じたときに特定の誰かに助けてもらう経験を重ねることで、子どもは助けてくれる大人、さらには助けてもらえる自分という存在を信じることができるようになるのです。この基本的な自他への信頼感が、自尊心や思いやりといった心の力の基礎になります。安定したアタッチメントのために、次のようなことを意識してみましょう。
子どもの「助けて」に応える
子どもが不安やストレスを感じて「助けて」のサインを出して来たら、しっかりと受け止めて、守ってあげましょう。
子どもにとって、困ったときはここに帰ってくれば大丈夫と思える基地になることが大切です。親や周りの大人がそのような安心できる基地になることで、子どもは様々なことにチャレンジできるようになります。忙しかったり、余裕がないときも子どもが避難してきたら「どうしたの?」と受け止めましょう。
スキンシップをする
子どもが不安な気持ちや怖い気持ちになっていたら、抱きしめたり、身体をさすったりして、安心させてあげましょう。
「怖かったね」「悲しかったね」
子どもの気持ちが落ち着いてきたら、どんな気持ちだったのかを想像して、気持ちを代弁してあげましょう。
気持ちにことばを与えることで、子どもは「自分は怖かったんだな」と理解できます。気持ちを表現することばが増えていくことで、自分の感情に気づいてケアしたり、人の気持ちを考えて思いやれるようになっていきます。
見守ってエールを送る「ここにいるよ」「見てたよ」
子どものよい基地となるには、待つことも必要です。
例えば公園で転んでしまったとき、「泣く」「不安そうにこちらを見る」といった「助けて」サインがあれば、基地として助けに行きましょう。
しかし、子どもが自分で立ち上がり、また楽しそうに遊び始めるならそっと見守ってみましょう。そして子どもが「見てくれているかな?」と確認するようにこちらを見たら「ここにいるよ!」「見てたよ!」「すごいね!」とエールを送りましょう。
大人の非認知能力を高める方法
非認知能力を高めるには、乳幼児期の経験が重要といわれています。
しかし大人になったらもう手遅れということはありません。大人が非認知能力を高めようとしたときに重要なことは自分の状態を観察する「内省」の力です。
まずは具体的に非認知能力のどの能力を伸ばしたいのかを考えてみましょう。そしてその伸ばしたい能力について、現状を観察、課題発見、解決策の実施、振り返り、第2の解決策の実施という試行錯誤を繰り返すことで、大人も非認知能力を向上させることができます。
例えば、「資格の勉強をしないといけないのに誘惑に負けてだらだらしてしまう」という場合、高めたい非認知能力は自制心です。下記は試行錯誤の例ですので、参考にしてみてください。
現状を観察
寝る前に勉強をしたいと思っているが、夕食の後はやる気が出ない。
課題を発見
夕食後はやる気が出ない。
解決策
夕食前に勉強をするようにしてみる。
振り返り
夕食前の方が勉強を始めやすい。しかしお腹がすいて集中がれやすい。
第2の解決策
クッキーなどを勉強のおともに用意する。
振り返り
毎日勉強する習慣をつけることができた。
このように、内省しながら解決策の実施とその振り返りを繰り返すこと、非認知能力を高めていくことができます。
非認知能力の重要性
非認知能力に最初に注目したのは、経済学の研究者でした。経済学の分野では、何に投資をすれば社会経済が発展するか」についての探求が広く行われています。
その中で、子どもがよりよい点数をテストでとれるように教育投資をすることが、個人の社会的成功ひいては経済発展に有効だとされてきたのですが、自尊心や協調性など、認知能力ではない「心の力」も個人の社会的成功につながることがわかってきたのです。
ノーベル経済学賞ヘックマンの分析「ペリー就学前計画」
非認知能力が注目されたきっかけは、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者ヘックマンの分析です。
ヘックマンは「ペリー就学前計画」という研究の分析結果から、就学前の乳幼児期に適切な教育を受けることで「非認知能力」がより効果的に向上し、よりよい人生の実現につながると主張しました。
ペリー就学前計画では、1960年代にアメリカで行われた介入研究で、「幼児教育プログラムを実施した子どもたち」と「実施しなかった子どもたち」をその後40年にわたって追跡調査をすると、プログラムを受けた子どもたちの方が、犯罪率が低く、年収が高く、持ち家率が高いというようによりよい生活を送っていることが明らかになりました。
幼児期のほんの数年の経験が40年後の生活にここまで影響しているというのは驚きですよね。さらに興味深いことに、学力という「認知能力」で見てみると、プログラムを受けた子どもたちの方が、成績が良かったのは小学校低学年のうちだけで、その後は学力に差が見られなかったのです。
認知能力に差はみられなかったにも関わらず、その後の人生に差が見られたのは、教育プログラムによって自制心や粘り強さといった「非認知能力」に差が出たからだと考えられます。
OECDによる国際調査報告書
OECD(経済協力開発機構)は社会の発展と個人の幸福につながるよう能力とその教育について国際調査を行っています。
その中で、非認知能力は「身体的健康」、「精神的健康」、「幸福感」を高めることが明らかになっています。
また、「スキルがスキルを生む」という表現がされており、早い段階で非知能力を高めることで将来さらに非認知能力が高まっていくこともわかっています。つまり高い非認知能力は個人の中で蓄積されていくのです。
教育の場では認知能力が重要視されがちですが、認知能力と非認知能力の両方をバランスよく育むことが大切です。
記事の執筆者
大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程 修了
現在は企業や大学にて研究員として活動しながら精神科クリニックでのカウンセリングも行う
【資格】
・臨床心理士
・公認心理師
【現在の業務内容】
企業ではスタートアップからメンタルヘルス関連サービス事業をマネジメントし、心理士・研究員として経営、広報、プレスリリースの作成、開発、研究、統計分析含め幅広い経験を積んできました。論文をはじめ、専門書原稿、一般の方向けのHP記事の執筆、英文の専門書の日本語翻訳も行っています。
クリニックでは適応障害・うつ病・不安障害・強迫性障害・発達障害・不登校・対人関係などの問題を抱える患者さんの心理的相談業務を担当しております。
閲覧数・いいね数
閲覧数
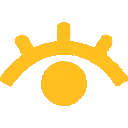
889
いいね

2
お役立ちコンテンツ
参考・外部リンク
遠藤利彦. (2017). 非認知的 (社会情緒的) 能力の発達と科学的検討手法について研究に関する調査報告書 (平成 27 年度プロジェクト研究報告書) (Doctoral dissertation, National Institute for Educational Policy Research).
https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/h28a/syocyu-2-1_a.pdf
遠藤利彦. (2019). アタッチメント:「非認知」 的な心の発達を支え促すもの. これから求められる非認知能力とは?, 21.
https://www.jfecr.or.jp/wp-cms/wp-content/uploads/2023/11/kiyou49.pdf
遠藤利彦. (2022). アタッチメントがわかる本:「愛着」 が心の力を育む. 講談社.
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000368567
Heckman, J. J. (2013). Giving kids a fair chance. Mit Press.
https://mitpress.mit.edu/9780262535052/giving-kids-a-fair-chance/
Johnson, S. C., Dweck, C. S., Chen, F. S., Stern, H. L., Ok, S. J., & Barth, M. (2010). At the intersection of social and cognitive development: Internal working models of attachment in infancy. Cognitive science, 34(5), 807-825.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1551-6709.2010.01112.x
OECD. (2022). Skills for social progress: The power of social and emotional skills.
https://www.oecd.org/en/publications/skills-for-social-progress_9789264226159-en.html
「 非認知能力」に関連する記事
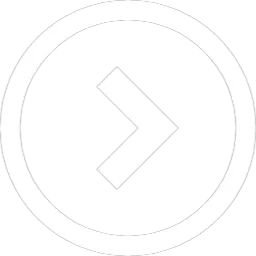
気になるテーマをすぐチェック!
Podcast「コドモトハナス」🎧✨
#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16
#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9
#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2
#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26
#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12
#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5
#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28
#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21
聞いた瞬間から使えます。おすすめ!
3~5歳が夢中になる!おすすめ絵本
児発・放デイ!事業所の紹介トップ
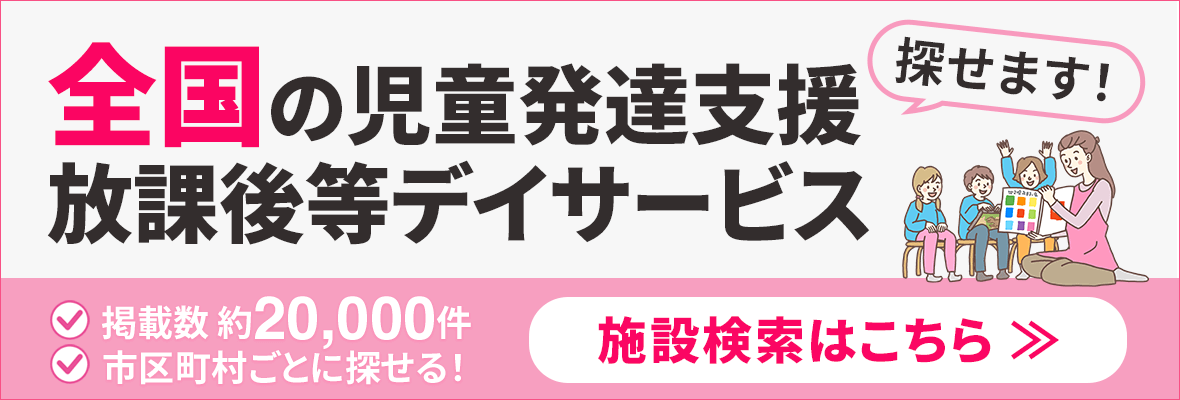




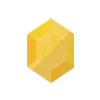
 「 非認知能力」に関連する記事
「 非認知能力」に関連する記事 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!