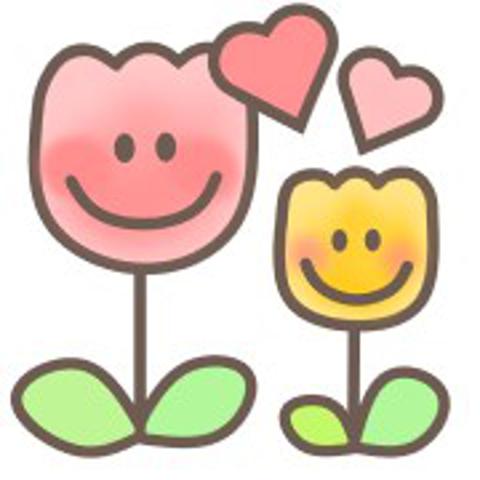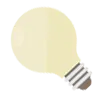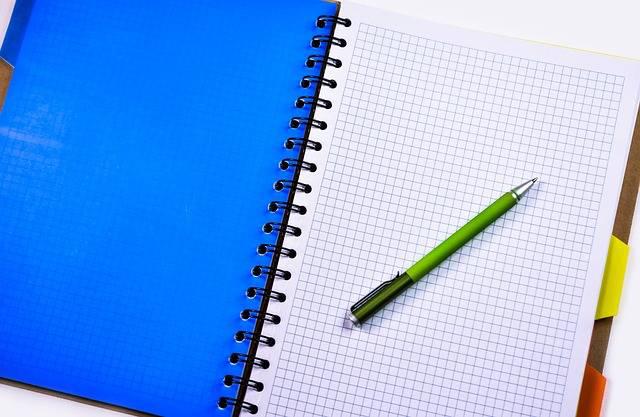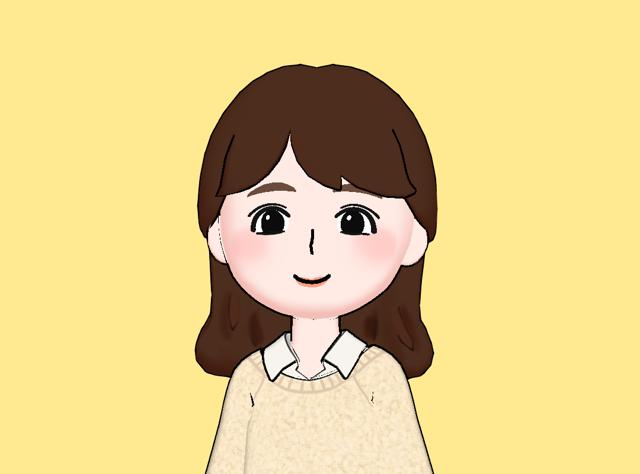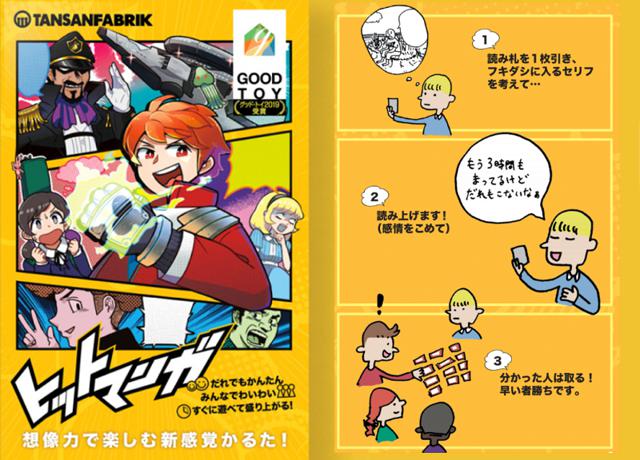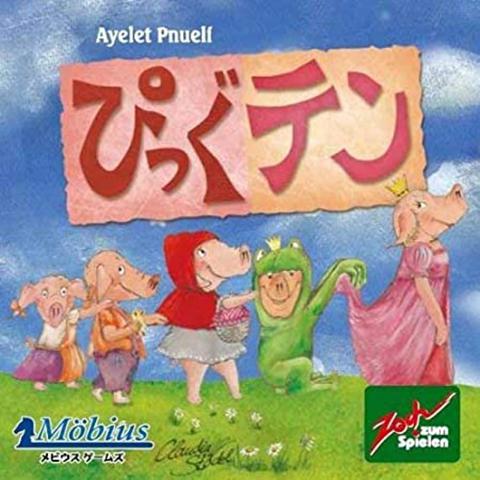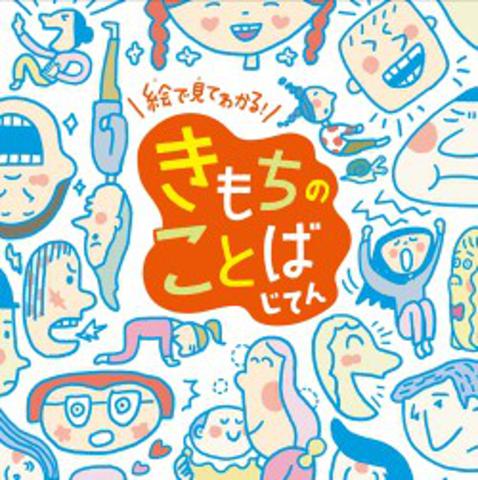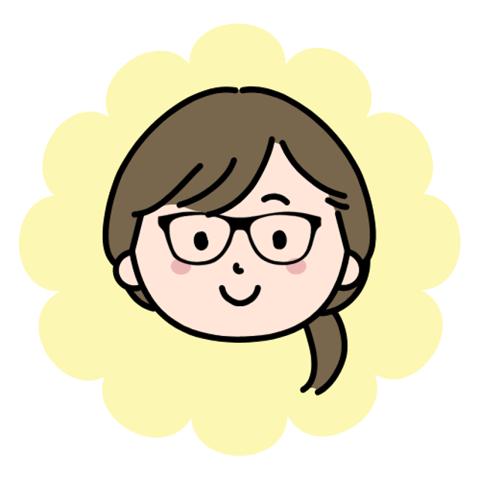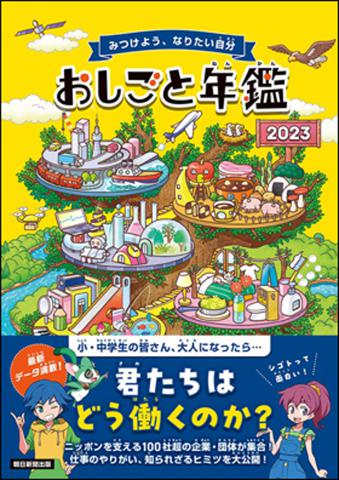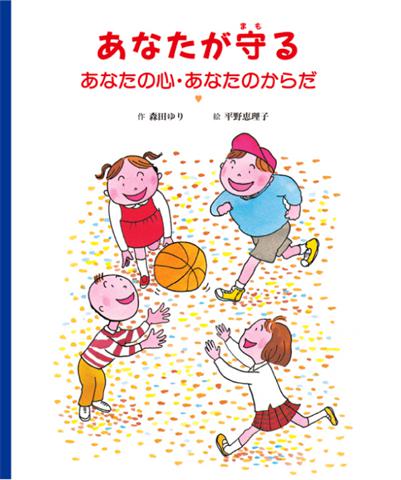| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |
| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |
忘れ物が多い子どもへの対策のコツは脳の負荷を減らしてあげること
記事の目次
サマリー
「うちの子しょっちゅう忘れ物をしている…」「忘れ物が多すぎる。」
多少の忘れ物は誰でもありますが、あまりにも頻繁だったり、ついさっきのことなのに覚えていなかったり、ということが続くと少し不安になりますよね。
例えば、
・先生の話を聞いていない
・聞いていても覚えていない
・連絡帳を書くこと自体を忘れる
・連絡帳やプリントを持って帰ってくるのを忘れる
・書いたことを忘れたり見るのを忘れたりメモ自体をなくしたりする
・時間割を揃えている途中で他のことをしてしまって忘れる
・カバンに入れ忘れる
・カバンの横においても持っていくのを忘れる
・手に持っていたのに靴を履くために手を離したらその間に忘れる
こんな調子で毎日のように忘れ物をしていると、ついつい叱りたくなるかもしれません。
でも、子どもはわざと忘れ物をしているわけではありませんし、どう気を付けたらよいのかわからず子ども自身も困っているものです。
一つの要因として脳のワーキングメモリが少ないということが考えられます。
この記事ではそのワーキングメモリについて説明をしつつ、子どもの脳の負荷を減らして忘れ物が少なくなるような仕組みを提案しています。
記事の執筆者
子どものワーキングメモリとは?
ワーキングメモリとは、必要な情報を一時的に脳の中に記憶しておく能力のことです。
頭の中にある机の大きさとイメージするとわかりやすいです。小さな机では、教科書を開いてからノートを開こうと思っても同時に開くことができず、教科書が机からこぼれ落ちてしまいます。
このように同時にいくつかの作業をしようと思っても、一つ何かを始めると前にしていたことを忘れてしまうので、効率よく進めることが難しくなってしまいます。
こういうお子さんにとって、次の日の持ち物を覚えておきながら家に帰ること、気をそらさずに最後まで持ち物を用意すること、などは大変な作業です。
忘れ物が多い子どもの脳の負荷を減らしてあげる方法

準備をする時間やタイミングを決めておく
帰ってきて宿題をしたらすぐに次の日の持ち物を準備しておやつを食べる、お風呂に入ったら次の日の服と持ち物を準備する、など毎日のルーティンに準備の時間を組み込みましょう。
学校の準備が出来たらおやつ、など、その次にお楽しみがあるとモチベーションが高まりダラダラせずにすみます。
できるだけおもちゃや余計なものが目に入らないシンプルな空間で準備する
準備をしている途中で面白そうなものや気になることが目や耳に入るとそちらに気がそれて準備することを忘れてしまいます。
持ち物をそろえるときに行ったり来たりしなくてよいように学校コーナーを作り、他のものは置かないようにしましょう。
ハンカチ、ティッシュ、名札、ランチョンマット、マスク、鉛筆、消しゴム、鉛筆削り、など毎日必ず使うもの、持っていくものを1か所にまとめておきましょう。
次の日に持っていくものをすべて一か所にまとめる
玄関の近くにカバンコーナーを用意し、翌日持っていくものをすべて一か所にまとめます。
ロッカーやカゴなど枠がはっきりしているもので、ランドセル、体操着、上履き、給食袋、絵の具セット、習字道具、などが入る大きさにしましょう。
「明日学校に持っていくものはみんなここに置こうね」と声を掛けます。家を出るときに、そこの場所のものがすべてなくなっていたら忘れ物なしです。
その場所には次の日に持っていくもの以外は置かないようにするため、下の段にその日持っていかない学校用具入れを作っておきましょう。
忘れたときに「〇〇忘れているよ」と教えてあげているといつまでもできるようにならないので、本人が自分で気づけるような声かけをしてあげましょう。
家を出る前に、
「今日は何を持っていくんだっけ?」
「持ち物全部持ったかな?」
「忘れ物ないか確かめよう」
などと声かけをします。
「持ち物チェックリストを作ってみよう」
と自分でチェックする練習もしてみましょう。
記事の執筆者
・大学、大学院にて臨床心理学を専攻
・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、
・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務
・家庭教師経験8年
【資格】
・臨床心理士
・公認心理師
・教員免許(中・高)
5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。
閲覧数・いいね数
閲覧数
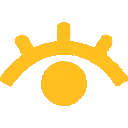
1467
いいね

200
お役立ちコンテンツ
「 忘れっぽい」に関連する記事
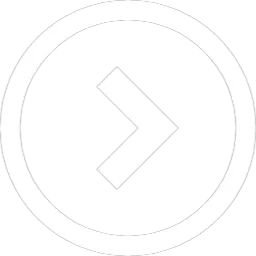
気になるテーマをすぐチェック!
Podcast「コドモトハナス」🎧✨
#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16
#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9
#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2
#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26
#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12
#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5
#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28
#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21
聞いた瞬間から使えます。おすすめ!
小学生が夢中になる!おすすめ絵本
児発・放デイ!事業所の紹介トップ
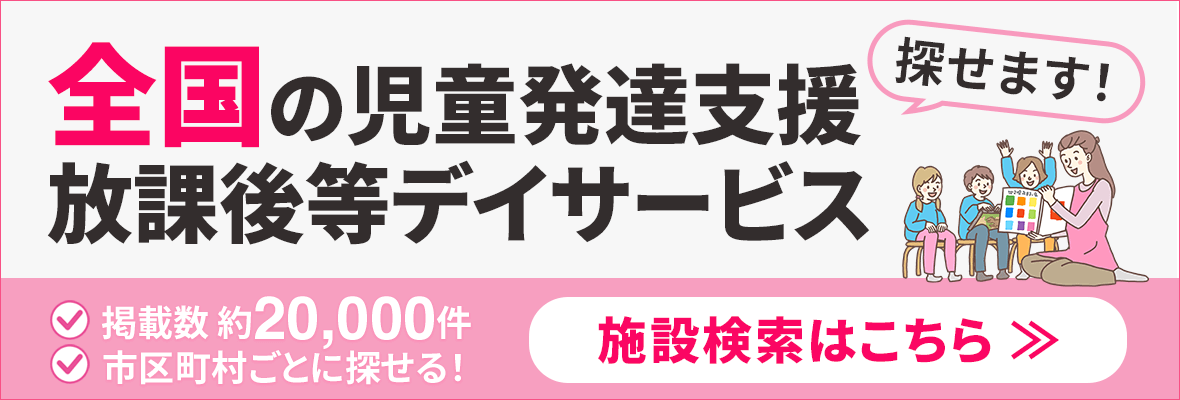




 「 忘れっぽい」に関連する記事
「 忘れっぽい」に関連する記事 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!