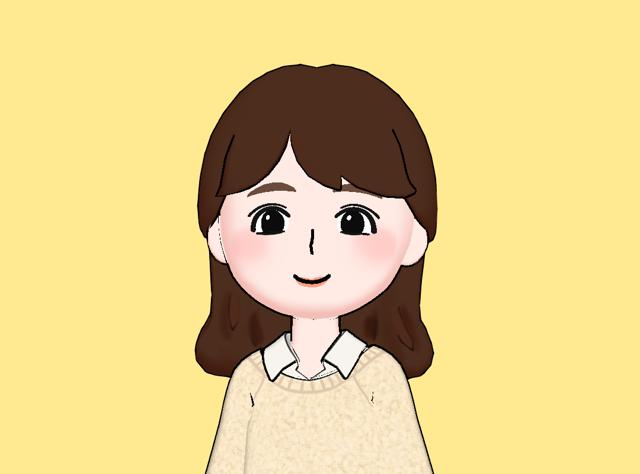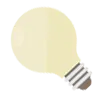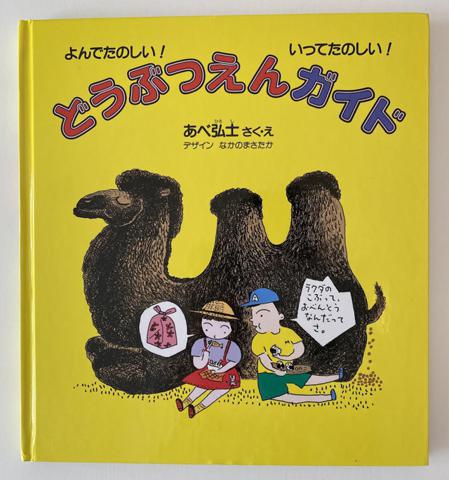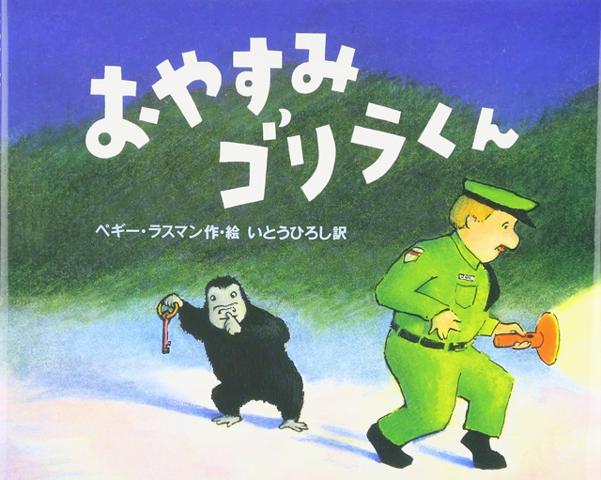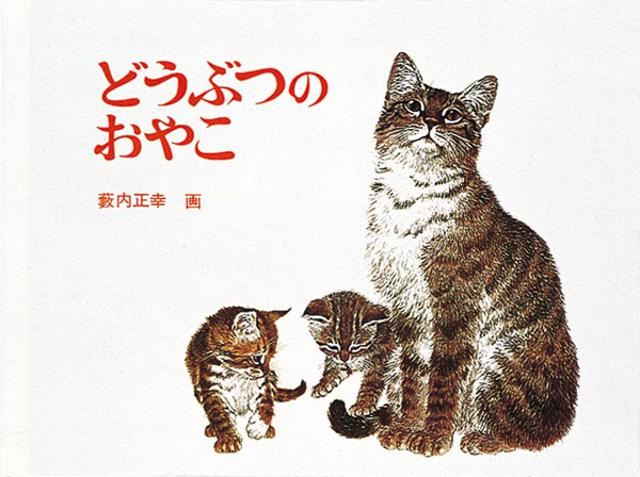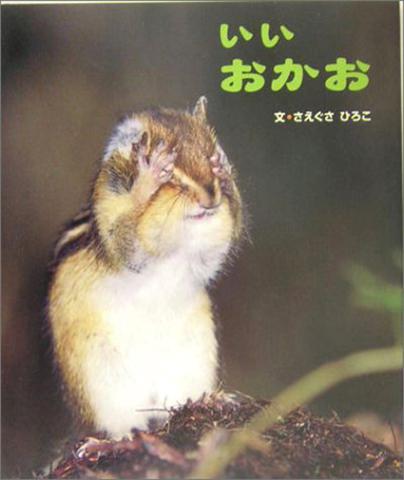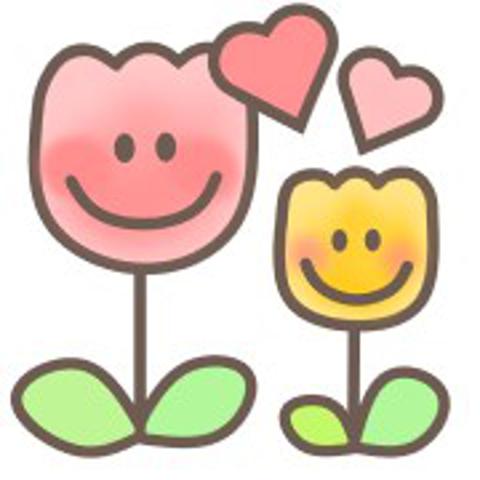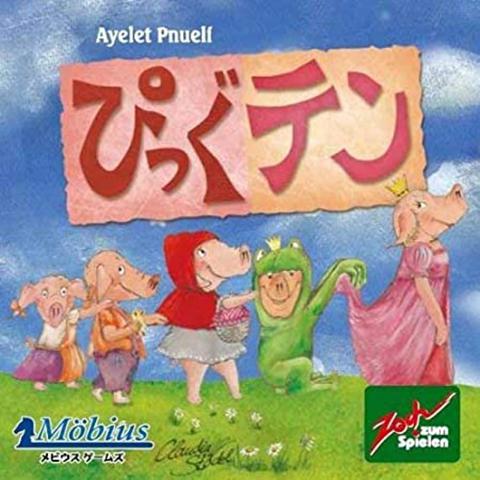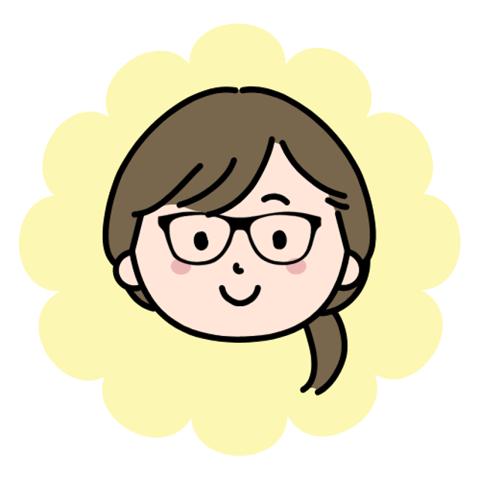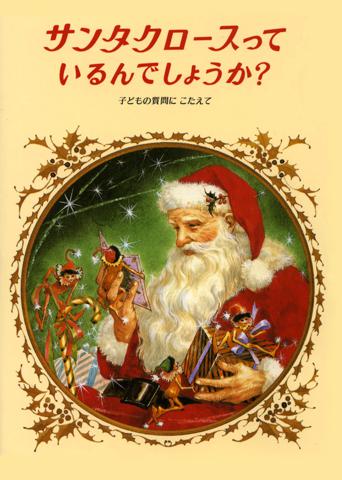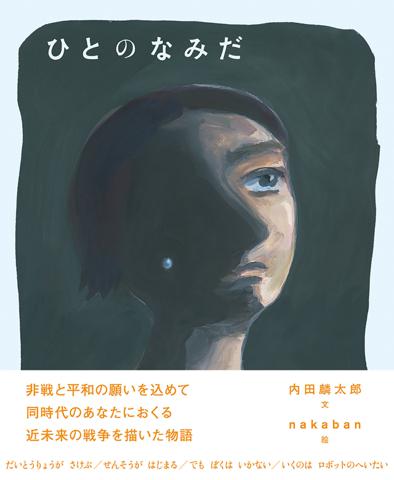| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |
| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |
小学生の自由研究におすすめ!メダカ観察のテーマとまとめ方完全ガイド
記事の目次
サマリー
この記事では、子どもの自由研究で何をしようか悩んでいるママとパパに対して、メダカの飼育・観察をおススメしています。また、メダカの観察を自由研究にする際の方法や、メダカ飼育を通じて行われる親子のコミュニケーション方法、そして、研究の簡単なまとめ方についても紹介しています。
なお、他にも小さな熱帯魚はたくさんいますが、グッピーやプラティはすごい勢いで増えて大変です。
メダカは丈夫で、人になつきますし、初心者でも飼いやすい生き物です。
今は品種改良されたキレイなメダカがたくさんいますので、選ぶ楽しさもあります。
アクアリウムが好きなママパパにもオススメです。
記事の執筆者
メダカの観察:小学生向けの研究方法とテーマ
研究では、個体そのものを見ていてもあまり新しい発見ができません。
他の何かと比較をすることによって「違い」を見つけ、それを深堀りすることで新しい「発見」となり、頭の中で理解されていきます。
比較して「違い」を見つける方法としては
①時間的な変化での比較
②個体同士の比較
③事前に立てた予想との比較
これらのやり方があります。
①メダカの時間的な変化の観察
季節
季節によってメダカの動きが異なるかどうかを観察します。
活発に泳いでいるか、元気にエサに食いつくか。水槽の上の方にいるか下の方にいるか。
周囲の寒暖差によって変わってくる動きについて観察し、その違いについて考えます。
時間帯
自由研究の課題があるのは夏であることが多いですね。
同じ夏でも、早朝と日中では気温が10度くらい異なります。時間帯によってメダカの動きに違いがあるか、エサの食いつきに違いがあるか、観察してみても面白いかもしれません。
成長記録
少し時間がかかりますが、小さいメダカが時間の経過とともにどのように成長していくかを観察します。
大きさは変わるか、色はどうか、何か違いは感じたか。それとも全然違うように見えないのか。
全然違うように見えなくても、それはそれで、「違いがない」という新しい発見です。
②メダカの個体ごとの違いの観察
メダカを複数飼う場合は、個体ごとの違いを観察することが出来ます。
例えば自由研究でメダカを買う場合、短い期間であまり違いが出ないかもしれない。と言う場合は、複数のメダカを飼育することで、個体ごとの違いを観察することをおススメします。
比較するポイントは
・大きさ
・形
・色
・動きの速さ
・エサへの食いつき
・水槽内での振舞い 等です。
③メダカについて事前に立てた予想との比較
メダカを飼う前に、事前に親子で情報収集をすることをおススメします。
事前に得た情報から予想を立てて、その予想と実際のメダカの違いを観察します。
予想通りでもいいですし、むしろメダカが事前に立てた予想と異なる動きをすれば、新しい発見に繋がるかもしれませんね。
メダカの観察:おススメの声かけ

メダカ飼育準備中
一緒にお迎えの準備をしてワクワクを共有しましょう。
メダカの飼育本を一緒に読んで、親子で学びましょう。おうちに新しい仲間をお迎えする、という気持ちを体験させ、メダカのためにどうすればいいのかたくさん想像させましょう。
「どんなものが必要かな?」
「メダカは何があったら喜ぶのかな?」
「メダカは何を食べるのかな?」
「メダカは何色かな?」
「4cmってどれくらいの大きさ?」
メダカを購入できるのは以下のような場所です。
・ホームセンター→種類は少ないですが気軽に買えます。
・アクアリウムショップ→種類が多く、店員さんも詳しいです。
・ジモティー→地元のメダカブリーダーさんが色々出品しています。
・道の駅→案外メダカコーナーがあります。
「元気な子のほうが長生きするんだよ」
「どの子がいちばん元気かな?」
と子どもによく見せて選ばせるのも良いと思います。
子どもが考えた名前をつけるのも良いです。
飼育している時
遠くから
「ほらーーメダカさんにエサあげてーー」
というのではなく、エサのフタをとって、子どもの眼の前に突き出し、
「はい。〇〇ちゃんがごはんくれるの、メダカが待ってるみたい」
と声をかけるとたいていやってくれます。
「ひとつまみね」と見本を見せると、ひとつまみの感覚も覚えてくれます。
美味しそうにパクパク食べてくれるので、
「ごはんおいしいって喜んでるのかな」
「お世話してもらって嬉しいのかな」
などとフィードバックしましょう。懐かれるのって嬉しい!と感じてもらいましょう。
発見を助けてあげる
小学校低学年や未就学児であればメダカを楽しく眺めているだけでもとても良いと思いますが、小学校の高学年などになってきたら、自由研究などに利用して、新しい「発見」や「考える事」を促すような声かけをしてもいいかもしれません。
「メダカは何で底の方に隠れているのかな。」
「昨日あげたエサが残っているよ。なんでだろう。」
「朝と夜で動きは同じ?違う?」
「全部同じに見えるけど、どう?ちょっと違う?」
「どの子が一番大きい?速い?」
メダカが亡くなったら
「病気かな。ケガかな。寿命かな。」
「わからないね。」
「でも、一生懸命お世話したから、メダカも幸せだったと思うよ」
とやさしく声をかけてあげましょう。
キッチンペーパーで丁寧にくるんでお庭に埋めたりして、ママパパが上手に処理してあげましょう。
みんなでメダカの可愛かったところや、お世話が大変だったところを口に出し合い、飼育過程を振り返りながら前を向くことが成長につながります。
メダカの観察:自由研究のまとめ方
①まとめ
この部分は、全体のまとめを書きます。なんでメダカの観察をすることにしたのか、どんな予想を立てて、結果はどうだったのか、そこから分かったことは何か。
②導入・きっかけ
ここには、なぜメダカの観察・研究をしようと思ったのかを記載します。
論文などでは、その研究が「なぜ必要なのか」という理由を説明する必要がありますが、自由研究で与えられた課題の場合は難しいですね。
③メダカの飼い方、観察期間、場所など
どのような環境で飼育をしていたのかを記載します。屋外なのか、屋内なのか。観察期間はいつからいつまでで、その時の気温はどうだったのか。などです。
④メダカに関する予想
事前に予想をしておくと、その予想と観察結果の比較をすることができます。
事前にインターネットや図鑑などで親子で見てみるといいと思います。
予想については、例えば
・エサは何を食べるか
・どれくらい生きるか
・1週間でどれくらい大きくなるか
・周りで大きな音を出したら反応するか
などなど、自由です。
⑤メダカの観察結果
観察した内容や、事前の予想との比較を書いていきます。
⑥わかったこと
観察した内容や、事前予想との比較を通じて感じたこと、その後に親子で調べて新しくわかったことなどをここに書いていきます。
⑦まとめ
メダカの飼育を通じて学んだこと、感じたことをここに書きます。
記事の執筆者
・認定心理士、臨床心理士、公認心理師の資格を取得
・医療と教育分野に10年以上従事する現役心理士
・子どもから高齢者までの幅広い臨床経験
・厚生労働省認可のもと公認心理師実習指導者として後進に育成にあたる
【職務経歴】
・教育委員会の教育相談
・国立、大学病院等の精神科、心療内科、神経科、児童精神科
・製薬会社の治験(新薬開発)における心理評価
【職務経歴】
・心理学の専門的知識
・心理相談、カウンセリング、心理療法、プレイセラピー
・心理検査(発達/知能/性格/認知/うつ/不安等)
・研究論文執筆や学会発表
・心理実習生の指導
・大学や研修会での講師
・Podcastラジオパーソナリティ
閲覧数・いいね数
閲覧数
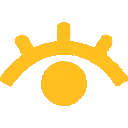
4999
いいね

4
お役立ちコンテンツ
「 動物」に関連する記事
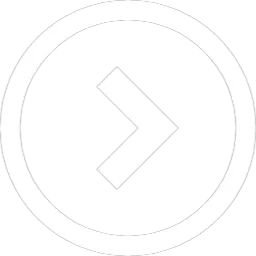
気になるテーマをすぐチェック!
- 動物 ( 57 )
- 自由研究 ( 4 )
- 生き物 ( 4 )
-
メダカ ( 1 )
- 飼う ( 2 )
- ペット ( 16 )
- 魚 ( 12 )
- 情操教育 ( 3 )
- 世話 ( 6 )
- いのち ( 13 )
- 死 ( 8 )
- 寿命 ( 2 )
- 思いやり ( 20 )
-
やさしさ ( 1 )
- 責任 ( 4 )
- 教育 ( 18 )
- 犬 ( 6 )
- 猫 ( 8 )
Podcast「コドモトハナス」🎧✨
#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16
#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9
#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2
#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26
#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12
#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5
#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28
#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21
聞いた瞬間から使えます。おすすめ!
小学生が夢中になる!おすすめ絵本
児発・放デイ!事業所の紹介トップ
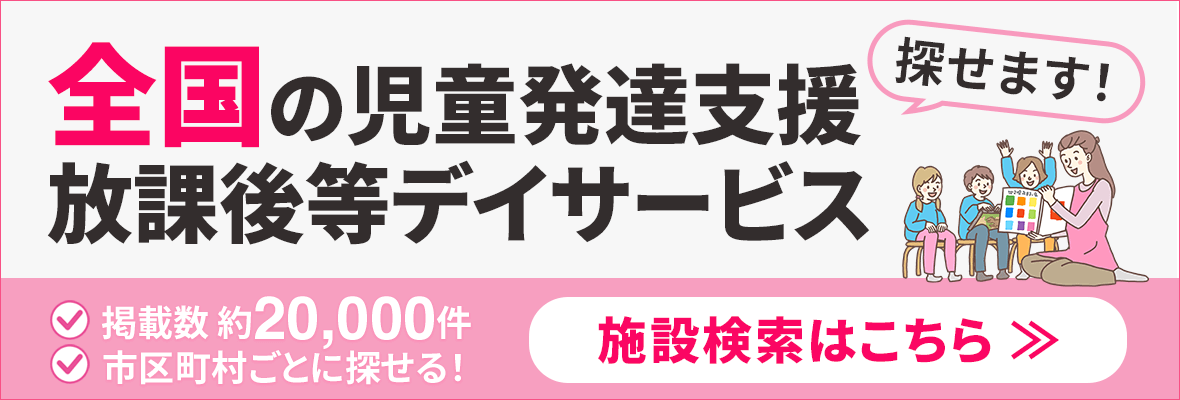




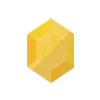
 「 動物」に関連する記事
「 動物」に関連する記事 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!