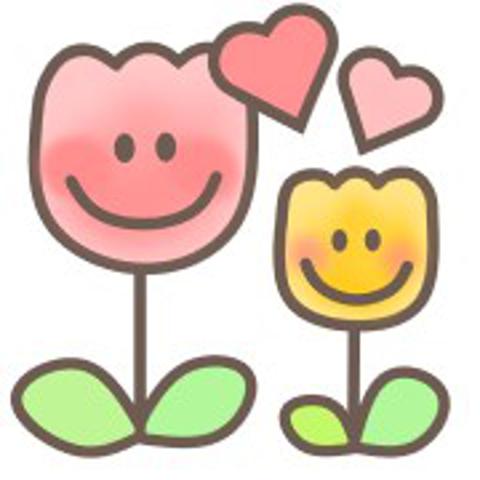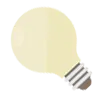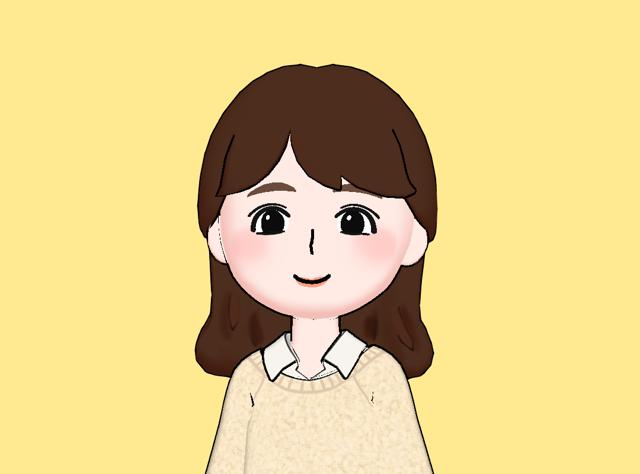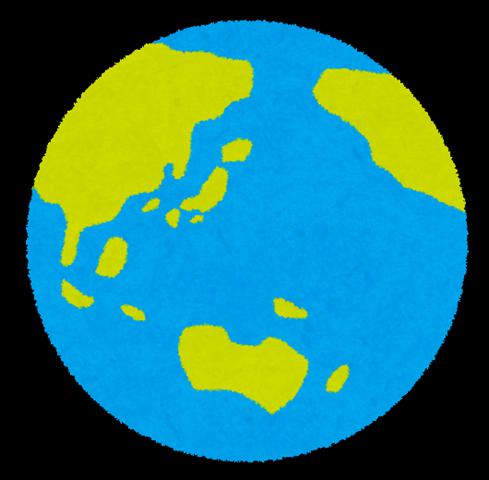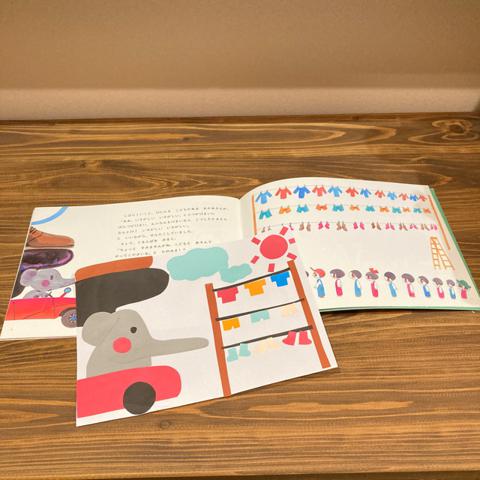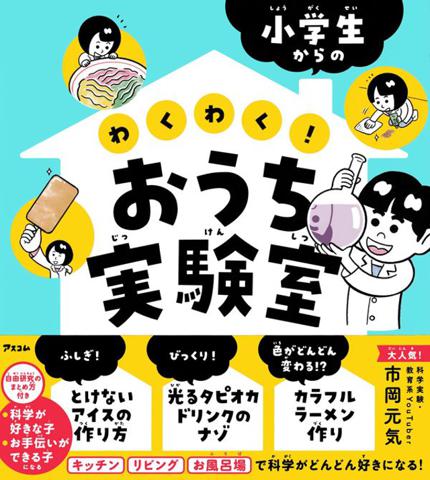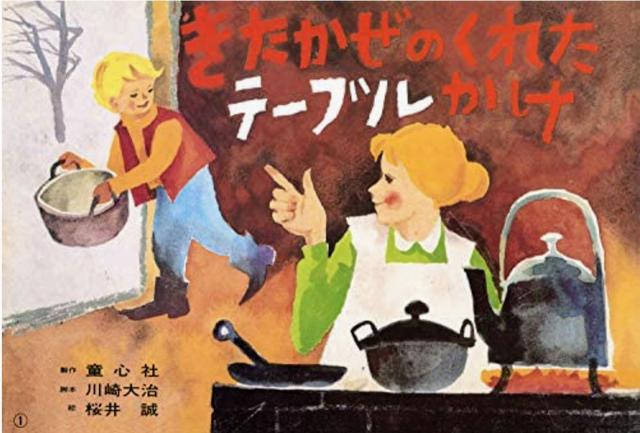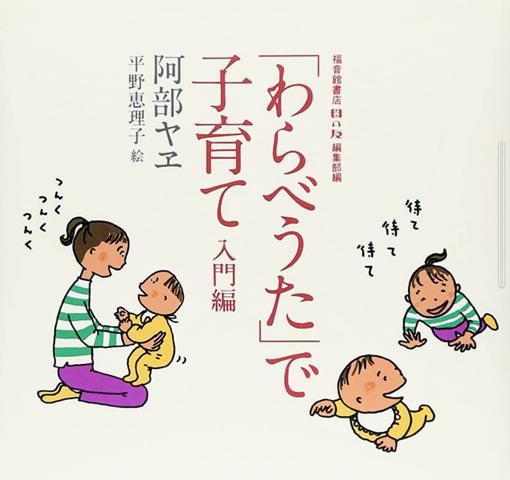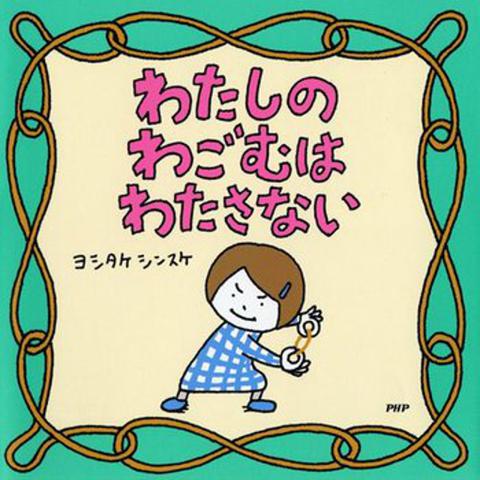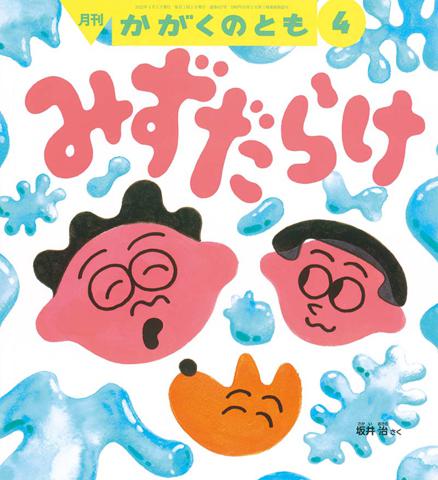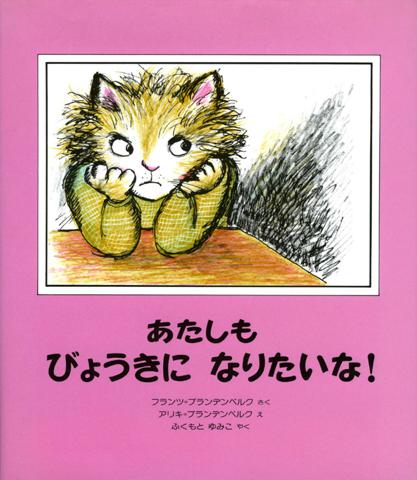| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |
| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |
3-5歳児の癇癪対策:睡眠不足が原因かも?効果的な解決方法を徹底解説
記事の目次
サマリー
子どもが癇癪を起こして泣き叫んだり暴れたりして何を言っても伝わらない時、とても疲れますし、無力感を感じますよね。そんな時は睡眠時間を見直してみませんか?癇癪は、いろいろな要因によって起こりますが、思い通りにならないときや不快な感情をうまく処理できない時などに起こりがちです。
また、お腹が空いている、疲れている、眠たい…など生理的な条件によっても癇癪が起こりやすくなります。
中でも注目してほしいのは睡眠の問題です。
癇癪を起こす多くの場合に、睡眠の問題が隠れていることがあります。
この記事では、癇癪と睡眠不足の関係について説明しつつ、どのように子どもに良い睡眠をさせていくか、その方法について解説していきます。
記事の執筆者
子どもの寝不足・睡眠不足と癇癪の関係
寝不足・睡眠不足の影響
睡眠不足の状態が続くと、酩酊状態と同じような脳の状態になってしまいます。
脳の機能が低下し、普段できていることでもうまく対処できなくなります。
また、感情のコントロールも働かずに爆発してしまいやすくなります。(私も寝不足の時はイライラして子どもを叱ってしまう確率が高い気がします)
子どもがなかなか寝てくれないと親もフラフラになりますが、お子さん自身も落ち着きがなくなったり抑制が効かなくなったりイライラしたりしやすくなります。
発達障害がある子どもの場合
発達障害があるお子さんの場合、癇癪を起こしやすいことが知られています。
そもそも対人関係を築くスキルや状況を考慮し見通しを立てて行動することに弱さがあったり、不器用さがあったりして、思い通りに行かない経験が多くなりやすくなります。
それに加えて発達障害のお子さんは睡眠障害を持つ場合が少なくありません。
寝つきが悪い、眠りが浅く夜中に何度も起きる、早朝に目が覚めてしまう…などです。
もともと持っている特性に加えて睡眠の問題で感情コントロールがさらに低下しやすくなり爆発することが多くなりやすいです。
すべてのお子さんではありませんが、睡眠リズムを正すことで癇癪が減り落ち着くお子さんも一定数いますので、一度見直してみてはいかがでしょうか。
子どもの寝不足・睡眠不足への対処法

眠る準備は朝から始まる!眠りを促すホルモンを味方につけよう!
自然な眠りにはメラトニンというホルモンが関係しています。
メラトニンはセロトニンを材料として作られています。
朝起きてしっかりと朝の光を浴びて軽いリズム運動をするとセロトニンが分泌されます。セロトニンは幸せホルモンと呼ばれ、心身をリラックスさせる効果があります。セロトニンが不足すると不安やイライラなどのストレスを感じやすくなります。
「朝起きてお日様の光を浴びると、イライラ虫が飛んでくよ!」
と声をかけて一緒にカーテンを開けて太陽の光を浴びるようにしましょう。余裕があれば朝のお散歩に出かけたり登園時に歩いたりするとより良いです。
セロトニンはトリプトファンとビタミンB6から作られますから、朝ごはんに大豆製品や乳製品、卵、バナナなどをとるとよいでしょう。
我が家は、冷蔵庫にトリプトファンやビタミンB6を含む食品を書いて貼っておき、「この中のものを毎朝たべようね」と声をかけています。
朝日を浴びて14~16時間ほど経つと、セロトニンは眠りを促すホルモンであるメラトニンに変わります。そうすると自然と眠くなって寝付きやすくなります。
ブルーライトを浴びるとメラトニンの分泌が抑制されてしまうので、夕方以降はテレビ、スマホ、タブレット、ゲームなどをできるだけ避けましょう。
副交感神経を高めてリラックス
副交感神経が優位になると、リラックスして眠くなりやすくなります。
早めに夕食とお風呂を済ませるようにしましょう。
お風呂でしっかりと身体を温めると入浴後90分くらいして体温が下がってきたときに入眠しやすくなります。
寝る前のルーティンを作り毎日繰り返すこともリラックスにつながります。
入眠儀式とも言いますが、トイレに行く、読み聞かせ、マッサージなど決まったパターンを毎日繰り返すことで、これをしたら寝る、というパターンを無意識に身体が覚えます。
睡眠環境を整える
室温、湿度、寝具、光、音など、不快な刺激があると眠りにつきにくくなります。
快適と感じられる環境を整えましょう。また、鼻詰まりなどが熟睡できない原因にもなりますので、体調を整えることも大切です。
以上、ご紹介したように家庭でできることをまずは試してみてください。
ただし、ADHDの子はメラトニンの分泌が遅れ、寝つきが悪くなりやすいこともあるようです。
また、癇癪の原因はもちろん睡眠だけではありません。
いろいろやったけど全然寝ない、家族の方が疲弊して体調を崩してしまう、かんしゃくがひどくて手におえないなどという状態の時は、無理をせず医療機関や専門家に相談しましょう。
記事の執筆者
・大学、大学院にて臨床心理学を専攻
・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、
・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務
・家庭教師経験8年
【資格】
・臨床心理士
・公認心理師
・教員免許(中・高)
5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。
閲覧数・いいね数
閲覧数
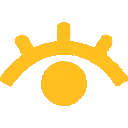
972
いいね

2
お役立ちコンテンツ
「 癇癪」に関連する記事
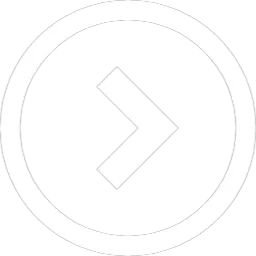
気になるテーマをすぐチェック!
Podcast「コドモトハナス」🎧✨
#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16
#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9
#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2
#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26
#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12
#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5
#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28
#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21
聞いた瞬間から使えます。おすすめ!
3~5歳が夢中になる!おすすめ絵本
児発・放デイ!事業所の紹介トップ
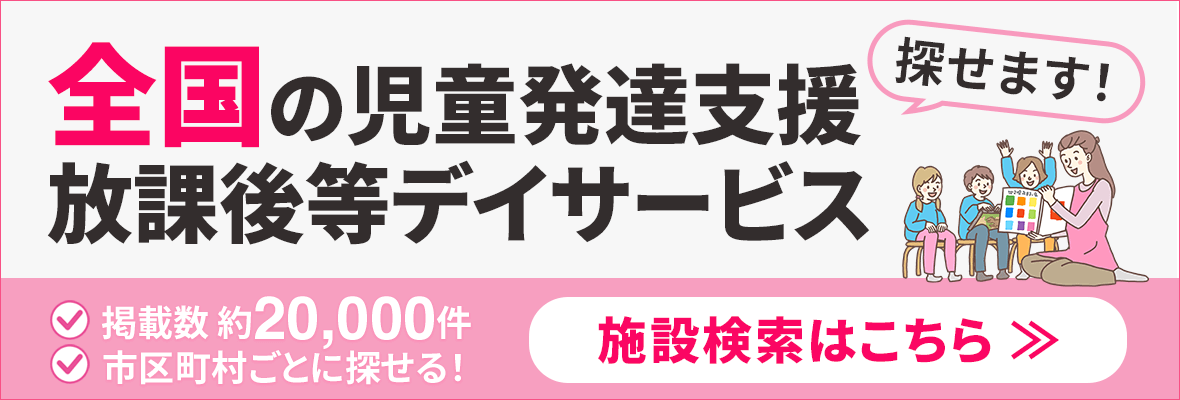




 「 癇癪」に関連する記事
「 癇癪」に関連する記事 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!