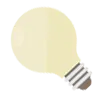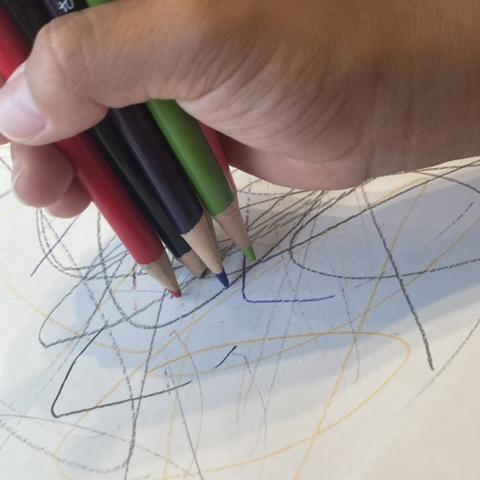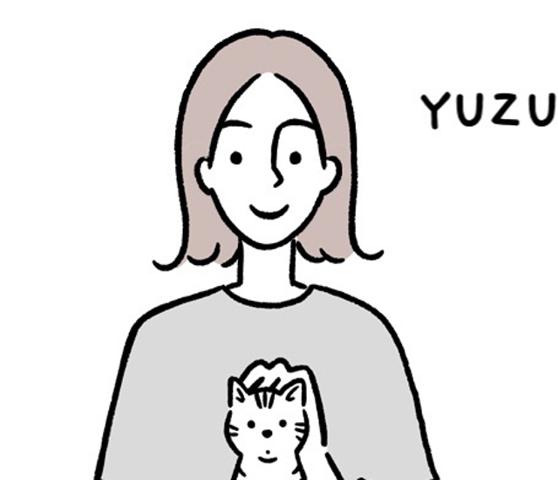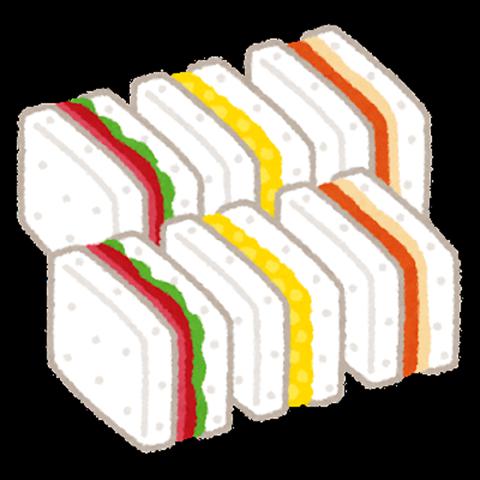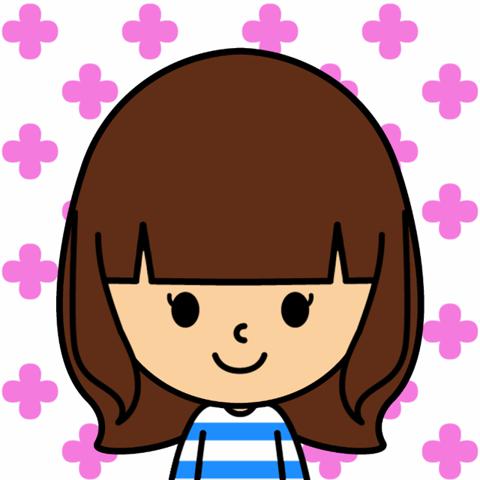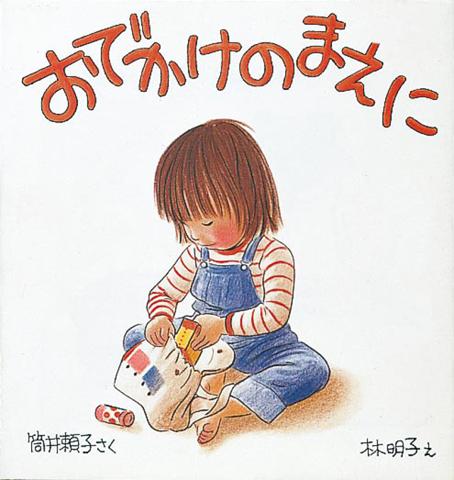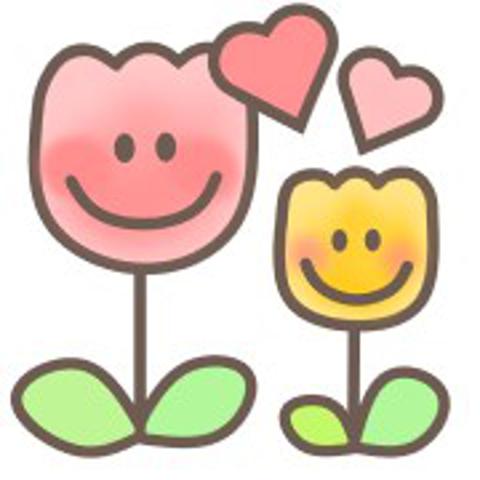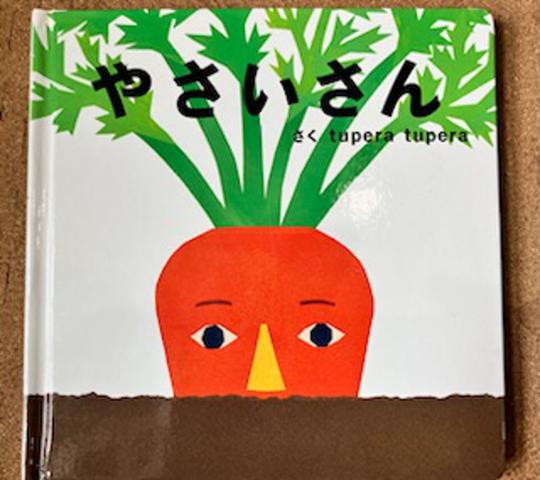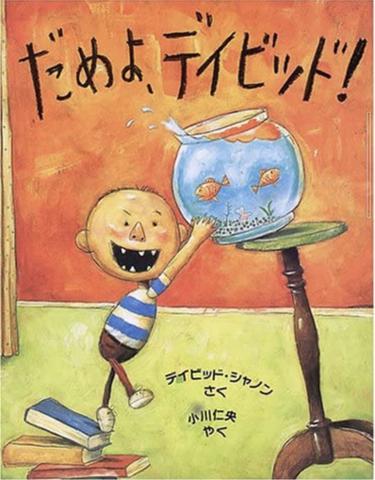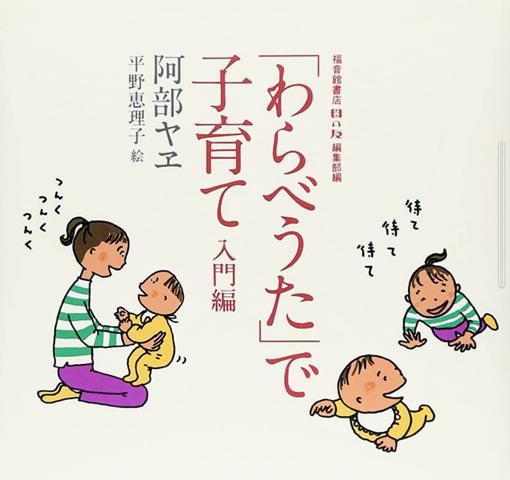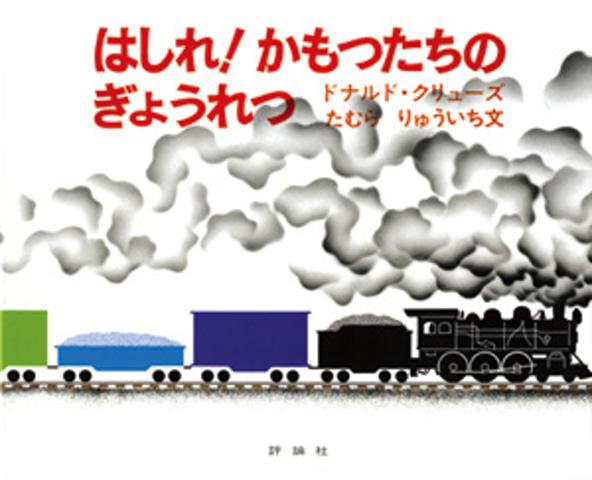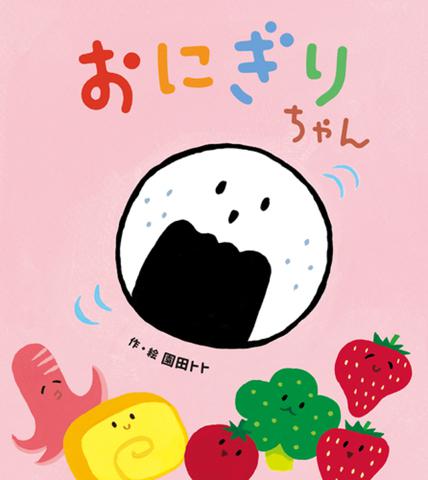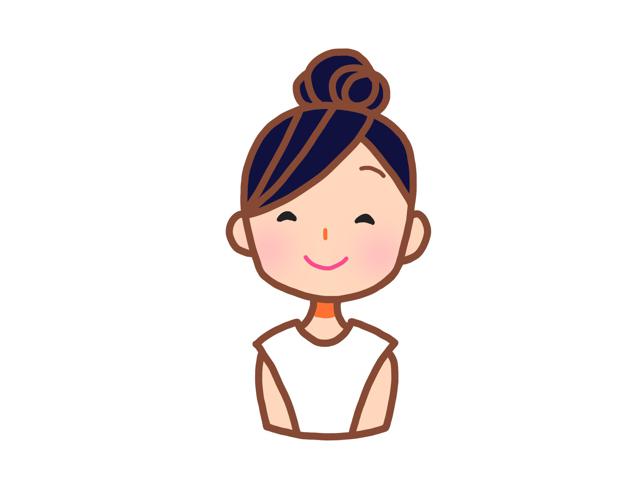| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |
| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |
子どもの癇癪は何歳まで続く?年齢別の対処法や予防法
記事の目次
サマリー
癇癪(かんしゃく)とは、欲求が満たされないときに感情をコントロールできず、大声で泣き叫んだりすることです。癇癪は自己主張ができている証であり成長の過程でどの子にも起こりうるものですが、その対応は親や周囲の人間にとってストレスフルなものになりがちです。
ここでは癇癪への対処法として安全を確保すること、感情を代弁すること、気持ちを立て直させる(切り替えさせる)こと等について解説しています。
また癇癪には予防も大切です。癇癪の要因を探して取り除いたり、自分の気持ちを癇癪ではなく言葉で表現できるようにサポートしてあげましょう。
子どもの癇癪が続くと「自分の育て方が悪いのでは…」と悩む方が多いです。
困ったときには一人で抱え込まず、誰かに相談することも大切です。自分を大切にしながらできる対処を模索していきましょう。
記事の執筆者
癇癪(かんしゃく)とは?
どんな行動が癇癪?
癇癪とは、何か嫌なことがあったときに、感情をコントロールできず、大声で泣き叫んだりすることです。
他にも頭をたたいたり、大人の気を引くような行動をとる等、その子によって癇癪の行動も様々です。
癇癪を起こすのは小さい子どもだけ?
癇癪は1歳から5歳ごろの子どもによくみられます。
ですが小学生や大人でも自分の欲求が満たされなかったときに癇癪を起こすことがあります。
癇癪は成長の過程でどの子どもにもおこるものです。
子どもの癇癪は何歳まで続く?年齢別の対処法や予防法

癇癪は一般的に、子どもが自分の感情を言葉で表現できるようになる3歳から4歳頃には落ち着いてくることが多いです。
個人差があるものの、就学前(5歳から6歳頃)になると、癇癪が徐々に減少する傾向が見られます。
しかし、子どもの性格や成長のしかたには個性がありますので普段の子どもの様子をみて、年齢にこだわらず効果がありそうなものを試してみましょう。
また、どの年齢でもまずは安全を確保し、癇癪を起している間に2次的なケガをしないよう注意することが重要です。
1歳の子どもの癇癪
この時期は自分の感情についての認識を構築していく段階です。
まだ自分の感情をうまく表現することができないため、思い通りにいかない状況にパニックに陥りやすくなります。
感情の立て直しを助ける
子どもが安心できるようにサポートしましょう。
抱っこや、好きなおもちゃや毛布など、癇癪を起している原因から気持ちをそらさせてあげられるようなものがおすすめです。
感情を表現できるように助ける
「もう大丈夫だよ」「嫌だったね」「怖かったね」と子どもが感じていたり考えていたりするだろうことを簡単な言葉で代弁して感情の認識を助けてあげましょう。
そうすることで癇癪行動ではなく言葉で自分の気持ちを表現できるように促します。
癇癪の要因を分析する
どんなときに癇癪が起こっているかを振り返り、癇癪が起こりやすい要因を取り除いておきましょう。
例えばお腹がすいたときに癇癪が悪化しやすいなら、小さなおにぎりやお菓子をあげるといった対策を試してみましょう。
2歳の子どもの癇癪
魔の2歳とも呼ばれるこの時期は、自己主張が強くなってくる時期です。
言葉が増えてきて感情を表現できるようになってきますが、まだ十分ではありません。
自分で選べるようにする
この時期の子どもは、親に「こうしなさい」といわれると不満が強くなります。
そのためできるだけ選択肢を与えて「自分で決めた」と子どもが感じられるように手助けしましょう。
例えばお出かけ時に癇癪を起こすときには「今日のお出かけはどっちの靴で行こうか?」とはきたい靴を自分で選べるように声をかけるのもよいでしょう。
ルールを作る
ルールを一緒に作っておくことも有効です。
例えば夜に「もう寝ようね」と急に声をかけられても「まだ寝たくない!」と癇癪につながるかもしれません。事前に「今日は8時に寝ようか」「じゃあ何時から寝る準備をしようか?」といったように、ルールやスケジュールを一緒に考えておきます。
すると子どもが自分でコントロールできているという感覚を持てるため癇癪が起こりにくくなります。「あと15分だよ」と予告してあげるのもよいでしょう。
3歳の子どもの癇癪
より言葉が増えて、自分の思いや感情を伝えることができるようになってきます。
社会性も芽生え始め友達との遊びの中で思い通りにならないことに直面することも増えてきます。
タイムアウト
癇癪には、大人の注意をひいて要求を満たそうとする側面もあります。
ここで要求にこたえていると癇癪行動がその子にとって有効な手段として学習されてしまう恐れがあります。
とはいっても、癇癪を起している子どもに「そんなことしても要求は通らないよ」と伝えても落ち着くことは難しいでしょう。
そこで、安全を確保したうえで、落ち着くまで時間を置きクールダウンさせるタイムアウト法が有効です。
あらかじめ落ち着きやすい場所や好きな毛布など、癇癪の原因から気持ちをそらしたり、落ち着けるようなものを決めておくとよいでしょう。
タイムアウトの後は「落ち着けてえらいね」とほめてあげましょう。タイムアウトの時間は年齢ごとに1分間が目安とされています(3歳なら3分間が目安です)。
感情を表現できるように助ける
タイムアウトの後には「怖かったのかな?」「怒っていたのかな?」など、感情を言葉で表現する手助けをしましょう。
自分の気持ちを癇癪ではなく、言葉で伝えることで問題を解決できるようにサポートしていきます。
4歳から5歳の子どもの癇癪
少しずつ社会的な状況に適応できるようになります。
認知的にも発達が進み、自分で考える力がついていきます。
問題解決を手助けする
癇癪の要因となっている感情がどういうものだったか一緒に話し合い、どうすれば癇癪行動以外の方法で解決できるかを子どもと一緒に考えてみましょう。
ルール作りやスケジュールの作成も役立つでしょうし、自分で気持ちを切り替える方法も準備できるとよいですね。
お気に入りの場所やぬいぐるみを使って自分で気持ちを持ち直す練習をしてみましょう。
友達との遊びの中で癇癪が起こる場合は、友達への気持ちの伝え方も一緒に考えていきます。
そうして癇癪行動以外の行動で状況に適応できるように手助けします。
小学生の子どもの癇癪
自分で感情を認識し、それを表現する力があります。
学校で生活する中で家族とだけでない自分の世界も持つようになっていきます。
問題解決を手助けする
小学生になると、友人関係が広がり直面する課題がより複雑になります。
子ども自身の自主性を尊重しながら、サポートしてあげる必要があるでしょう。
癇癪が起こった状況でどのように感じていて、次に同じ状況になったときにどうすればよいかを振り返られるように声掛けをしてみましょう。
はじめからいい考えが浮かばなくても、できそうなことから試して結果を振り返り、試行錯誤していくことが重要です。
子どもが新しい行動にチャレンジできたら「ナイスファイトだったよ」とほめてあげましょう。うまくいかないときも「ここが難しいね」「次はこうしてみるのはどうかな?」等とサポートしていきましょう。
ストレスマネジメントをする
子どももストレスが溜まっていると癇癪が起こりやすくなります。
学校生活で疲れがたまっていないか、疲れがたまっているようなら、運動や好きなことで気分転換したり、休息をとれるようにしましょう。
癇癪がおきる背景や要因
癇癪は欲求が満たされなかった場面で起こります。例えば、遊びに行きたかったのに行けなかったり、ほしいものが手に入らなかったり。
他にも、疲れていたりお腹がすいていても癇癪が起こります。
癇癪は一度起こるとなかなか止めるのが難しいものです。
その子がどういうときに癇癪を起しやすいのかを知って、対策していきましょう。
癇癪と発達障害との関係は?
癇癪は発達の過程でどの子にも生じうるものですので、癇癪があるから発達障害であるということはありません。
しかし、こだわりが強かったり、感覚が過敏だったりというような発達障害の特性が癇癪の要因になっていることがあります。
発達障害は脳の機能に問題が生じている疾患です。
癇癪の要因となりやすい発達障害には次のようなものがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDでは不注意(気が散りやすい)、多動症(じっとしていられない)、衝動性(衝動的に行動してしまう)がみられます。
特に幼児期にはよくぐずり泣く、抱っこを嫌がる、なだめにくい、常に体を動かしているといった様子がみられることがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)
ASDでは社会性と対人関係の障害、コミュニケーションや発達の遅れ、行動や興味の偏り(こだわり)、感覚の過敏がみられます。
そのため直前の予定変更や、苦手な音や声が刺激となり癇癪が起こりやすくなります。
発達障害が要因となっている場合も、癇癪が置きやすい状況を分析し、発達障害のどのような特性が癇癪に関係しているかを把握することが重要です。
癇癪で困ったときに頼れる相談先は?
癇癪は子どもが気持ちのコントロールができずに困っているサインです。
しかし長時間泣き続けたり、耳をつんざくような声を繰り返し聞くことは親にとって非常につらいものです。
余裕がなくつい強い言葉で叱って自己嫌悪になり、「自分の育て方が良くないのではないか」と悩む方も多いですが、癇癪は成長の過程でだれもが通りうる道です。
一人で抱え込まないで、誰かに相談したり、自分の時間を作ってリフレッシュしたり、自分のことも大事にケアしてくださいね。
癇癪で困ったときに利用できる相談先には次のようなものがあります。
どれも基本的に無料で相談ができますので気軽に利用してみましょう。
自治体の相談窓口
各自治体には子育てについて無料の相談窓口が設置されています。
保健師や助産師と話をすることができますので、自治体のHPを確認してみましょう。
児童相談所・こども家庭センター
児童相談所というと、虐待の通告などをイメージされるかもしれませんが、18歳未満の子どもの養育について様々な相談に応じてくれます。
学校・スクールカウンセラー
小学生の場合は、スクールカウンセラーや学校の先生に相談するのもよいでしょう。
学校での様子を知ってくれているので、より具体的な対策を考えやすくなります。
地域子育て支援センター
特に孤立しやすい3歳未満の子どもを育てている親子を対象に、気軽に子育てについて相談できるようにと設置されている施設です。
また同じ子育て中の方と交流の場にもなっています。
記事の執筆者
大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程 修了
現在は企業や大学にて研究員として活動しながら精神科クリニックでのカウンセリングも行う
【資格】
・臨床心理士
・公認心理師
【現在の業務内容】
企業ではスタートアップからメンタルヘルス関連サービス事業をマネジメントし、心理士・研究員として経営、広報、プレスリリースの作成、開発、研究、統計分析含め幅広い経験を積んできました。論文をはじめ、専門書原稿、一般の方向けのHP記事の執筆、英文の専門書の日本語翻訳も行っています。
クリニックでは適応障害・うつ病・不安障害・強迫性障害・発達障害・不登校・対人関係などの問題を抱える患者さんの心理的相談業務を担当しております。
閲覧数・いいね数
閲覧数
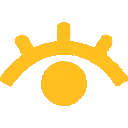
1610
いいね

2
お役立ちコンテンツ
参考・外部リンク
Potegal, M., & Davidson, R. J. (2003). Temper tantrums in young children: 1. Behavioral composition. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 24(3), 140-147.
https://centerhealthyminds.org/assets/files-publications/PotegalTemper1DevelopmentalAndBehavioralPediatrics.pdf
Daniels, E., Mandleco, B., & Luthy, K. E. (2012). Assessment, management, and prevention of childhood temper tantrums. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 24(10), 569-573.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23006014/
村上佳津美. (2017). 注意欠如・多動症 (ADHD) 特性の理解. 心身医学, 57(1), 27-38.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/57/1/57_27/_pdf
石塚誠之, 金曽美来, 小林楓花, 帯川大輝, 小山茉由, 應矢志保, & 増子智也. (2021). 癇癪行動を呈した発達障害児への行動支援の効果―PBS に基づくアプローチによる検討―. 北海道特別支援教育研究, 15, 23-32.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsneh/15/0/15_23/_article/-char/ja
「 癇癪」に関連する記事
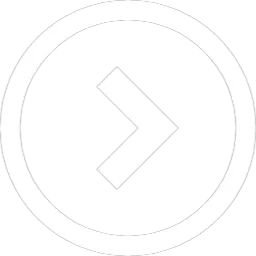
気になるテーマをすぐチェック!
Podcast「コドモトハナス」🎧✨
#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16
#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9
#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2
#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26
#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12
#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5
#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28
#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21
聞いた瞬間から使えます。おすすめ!
0~2歳が夢中になる!おすすめ絵本
児発・放デイ!事業所の紹介トップ
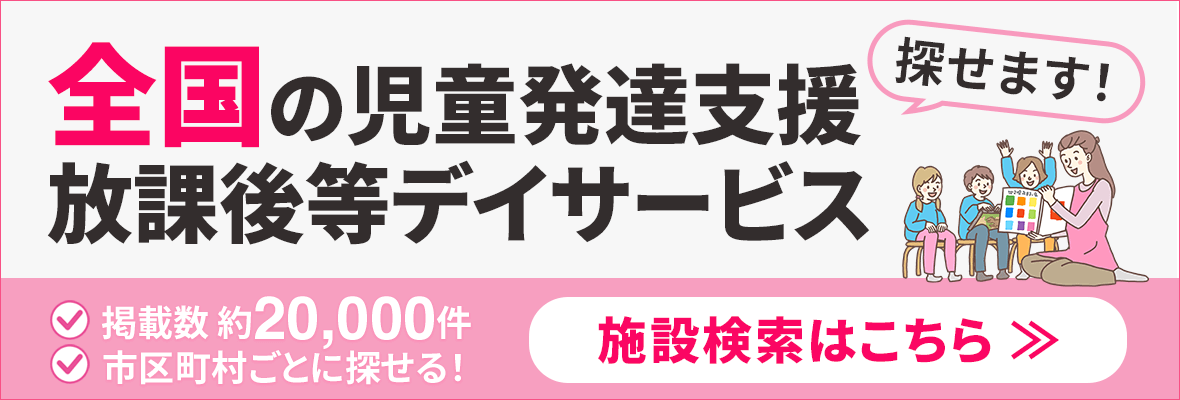




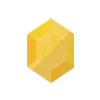
 「 癇癪」に関連する記事
「 癇癪」に関連する記事 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!