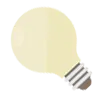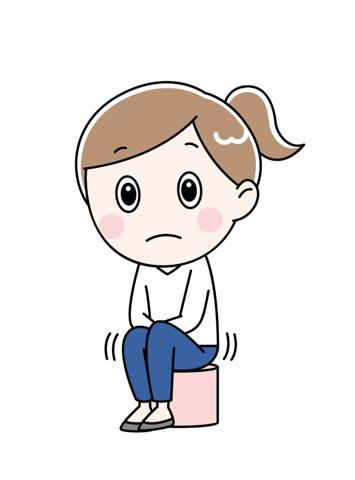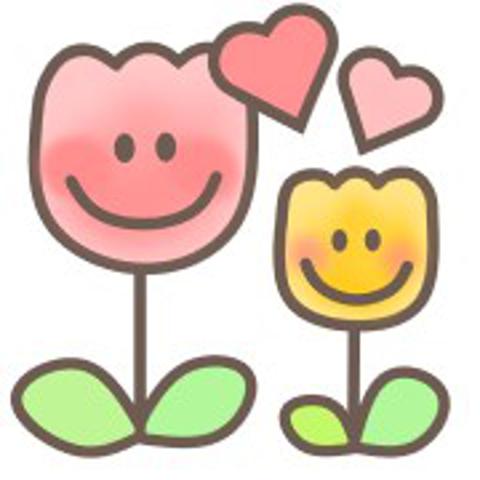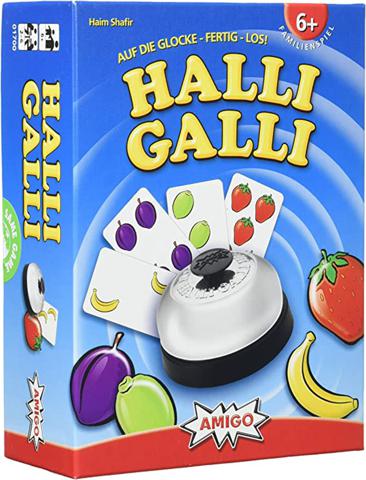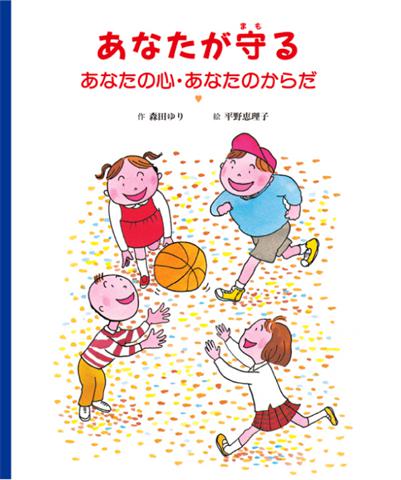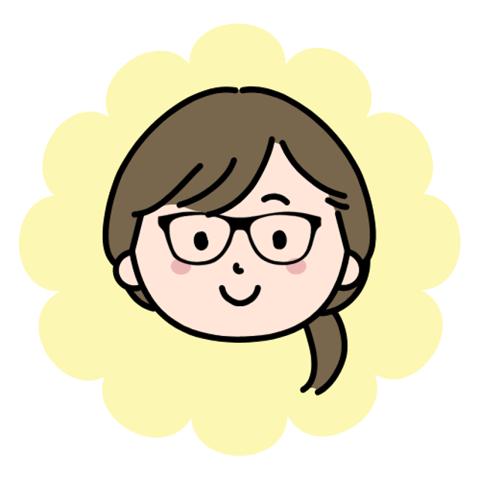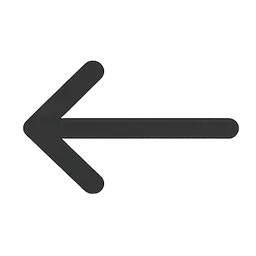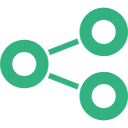【小学生】集団生活が苦手で不安やストレスを抱える子への我が家でのサポート方法
最終更新:2024.06.28
記事の目次
サマリー
子どもが幼稚園や小学校に通うようになると、集団生活に溶け込んでいけないケースがあります。この記事では、当初「集団生活は経験の積み重ね」だと考え子どもを学校に行かせていた方針を見直し、可能な限り子どもに合った環境や方法を模索した例を紹介しています。
記事の執筆者
もっと見る
まずはここから
これまで家族との生活が中心だった子どもが園や学校に通い始めると、
「お友達はできるかな」
「先生の話を聞いてみんなと行動はできているのか」
などと親は気になります。
お迎えに行くと先生から
「落ち着きなくフラフラしてました」
「またお友達とトラブルになってしまって、、」
などと報告を受けて落ち込んでしまう親御さんも多いかと思います。
わたしには、発達に大きな凸凹のある8歳の息子がいます。
言葉でのコミュニケーションや指示の理解も正確で、社会生活をおくるにあたり、著しく支援の必要はないので、公立の小学校に在籍しています。
けれども、教室や人の多い場所へ行くと不安や緊張が強くなり、感情のコントロールが思うようにいかず、耳を塞いでその場でうずくまってしまうことがあります。
このように、他者からは見えづらい困難さを持っており、本人は人知れず苦しんでいます。
発達に凸凹があったり、想像力や感受性の豊かな子は
“みんなと同じ”の意図が理解しづらかったり、疑問に感じてしまったり、
”みんながなんとなくやっている”ことでも
不安やストレスを強く感じてしまいます。
なぜ、我が子は集団行動が苦手なのか、どうしたら集団生活に入ることができるのか、または、集団生活に慣らすことばかり考えず、本人のペースを尊重して成長を見守る方がいいのか。
ではどの程度本人のペースを尊重するのか。
我が家での集団生活に対しての向き合い方や、サポートの仕方をご紹介します。
こんな「声かけ」がおすすめ!

無理しなくていいよ。疲れたら休もう。
集団生活とは、まとまった人の集まりの中で秩序を守りながら一定の期間共に生活をすることです。
ある程度長期にわたって集団生活での変化が見られない時は、何らかの困難や苦手さを持っているので、配慮や環境の見直しが必要です。
要因として下記の事が考えられます。
・不安や緊張が強い
(母子分離不安が強い。人のいる場所の雰囲気等で心臓がドキドキしてしまい情緒不安定になる)
・感覚や聴覚の過敏さがある(友達の声、給食のにおい等)
・感情のコントロールが苦手(嫌な経験をしたことがいつまでも記憶に残っていて、気持ちの切り替えができない等)
・性格、個性がはっきりしている
(内向的、引っ込み思案、自己中心的、目立つのが好き等)
・集団行動に順応できる発達年齢に達していない。または発達のペースがゆっくり
私自身の経験をお話しすると、
“集団生活は経験の積み重ね”
“成長段階には必要なことなので、ここが踏ん張りどころ!”と、
息子がどんなに嫌がっても毎日園や学校に行かせていました。
「もう疲れた。休みたい」
「誰も僕のことを理解しようとしてくれない」
息子は次第に暴力的になり、私にハサミやナイフを向け、自己否定を繰り返すようになりました。
一方で、
「集団生活は慣れだから」
「甘やかさない方がいいですよ」
周囲からはそんな声もあり、私自身も心が揺れ、何を信じたらいいのか分からず子育てに自信をなくしていました。
けれども、目の前の息子がこんなにストレスを抱えているのに、このまま無理にでも集団生活を続けてもいいのか。
なにか理由があるのか、少しずつ息子の声に耳を傾けることにしました。
「友達はほしいけど、仲間外れにされているみたいで、ぼくなんかビリビリに破かれた漫画の1ページみたいに、いっつも部屋の片隅に置き去りにされてるんだよ」
「朝だけなら学校には行けるよ」
「療育は個別なら大丈夫。勉強したり運動するのは好き」
息子の言葉から好きなことや苦手なことを手探りで拾い上げ、可能な限り彼に合った環境を探し、見直す事で、少しずつですが表現も明るくなり、癇癪も減っていきました。
正門をくぐることが出来なかった学校にも自分から足が向くようになり、
療育では個別プログラムに真剣に取り組み、先生との会話を楽しんでいるようです。
「無理しなくていいよ」
「疲れたら休もう」
「一緒に考えていこうね」
わたしは、息子に長い間、この言葉をなかなか言う事ができませんでした。
もしかしたら、
“このまま学校に行けなくなるんじゃないか”
“家から出られなくなるんじゃないか”
“立ち止まったらいけない”
そう思って私も少し無理していたのかも知れません。
園や学校以外にも視野を広げれば、地域の行事や子どもの居場所、多世代交流など、さまざまな場所で人との交流を持つことができます。
大人が視点を変えると、親も子供も自分たちらしく世界が広がるような気がします。
息子は、平日の昼間家で過ごすことの多いホームスクーラーです。
我が家がホームスクールを選択した経緯、学校との関わり、家でどのようにサポートしながら成長を見守っているか等については、別の記事でご紹介させていただきます。
ある程度長期にわたって集団生活での変化が見られない時は、何らかの困難や苦手さを持っているので、配慮や環境の見直しが必要です。
要因として下記の事が考えられます。
・不安や緊張が強い
(母子分離不安が強い。人のいる場所の雰囲気等で心臓がドキドキしてしまい情緒不安定になる)
・感覚や聴覚の過敏さがある(友達の声、給食のにおい等)
・感情のコントロールが苦手(嫌な経験をしたことがいつまでも記憶に残っていて、気持ちの切り替えができない等)
・性格、個性がはっきりしている
(内向的、引っ込み思案、自己中心的、目立つのが好き等)
・集団行動に順応できる発達年齢に達していない。または発達のペースがゆっくり
私自身の経験をお話しすると、
“集団生活は経験の積み重ね”
“成長段階には必要なことなので、ここが踏ん張りどころ!”と、
息子がどんなに嫌がっても毎日園や学校に行かせていました。
「もう疲れた。休みたい」
「誰も僕のことを理解しようとしてくれない」
息子は次第に暴力的になり、私にハサミやナイフを向け、自己否定を繰り返すようになりました。
一方で、
「集団生活は慣れだから」
「甘やかさない方がいいですよ」
周囲からはそんな声もあり、私自身も心が揺れ、何を信じたらいいのか分からず子育てに自信をなくしていました。
けれども、目の前の息子がこんなにストレスを抱えているのに、このまま無理にでも集団生活を続けてもいいのか。
なにか理由があるのか、少しずつ息子の声に耳を傾けることにしました。
「友達はほしいけど、仲間外れにされているみたいで、ぼくなんかビリビリに破かれた漫画の1ページみたいに、いっつも部屋の片隅に置き去りにされてるんだよ」
「朝だけなら学校には行けるよ」
「療育は個別なら大丈夫。勉強したり運動するのは好き」
息子の言葉から好きなことや苦手なことを手探りで拾い上げ、可能な限り彼に合った環境を探し、見直す事で、少しずつですが表現も明るくなり、癇癪も減っていきました。
正門をくぐることが出来なかった学校にも自分から足が向くようになり、
療育では個別プログラムに真剣に取り組み、先生との会話を楽しんでいるようです。
「無理しなくていいよ」
「疲れたら休もう」
「一緒に考えていこうね」
わたしは、息子に長い間、この言葉をなかなか言う事ができませんでした。
もしかしたら、
“このまま学校に行けなくなるんじゃないか”
“家から出られなくなるんじゃないか”
“立ち止まったらいけない”
そう思って私も少し無理していたのかも知れません。
園や学校以外にも視野を広げれば、地域の行事や子どもの居場所、多世代交流など、さまざまな場所で人との交流を持つことができます。
大人が視点を変えると、親も子供も自分たちらしく世界が広がるような気がします。
息子は、平日の昼間家で過ごすことの多いホームスクーラーです。
我が家がホームスクールを選択した経緯、学校との関わり、家でどのようにサポートしながら成長を見守っているか等については、別の記事でご紹介させていただきます。
はじめまして、まめぐっかと申します。
小学生の男の子ママです。
息子は、予定日より4ヶ月早い23週で生まれたNICU卒業生。
発達に凸凹があり、ほんの少し支援が必要です。
現在は、学校と学校以外の居場所で過ごすことを選択したホームスクーラーです。
私自身、専門的な資格や知識はありませんが、子育て中のお父さん、お母さんと同じ目線で、日々の声かけや、「笑顔になったよ!」っていうような寄り添い方について発信していきたいと思います。
“今も、これからも、あなたはあなたのままでいい”
そんな気持ちを大切にしながら見守っています。よろしくお願い致します。
小学生の男の子ママです。
息子は、予定日より4ヶ月早い23週で生まれたNICU卒業生。
発達に凸凹があり、ほんの少し支援が必要です。
現在は、学校と学校以外の居場所で過ごすことを選択したホームスクーラーです。
私自身、専門的な資格や知識はありませんが、子育て中のお父さん、お母さんと同じ目線で、日々の声かけや、「笑顔になったよ!」っていうような寄り添い方について発信していきたいと思います。
“今も、これからも、あなたはあなたのままでいい”
そんな気持ちを大切にしながら見守っています。よろしくお願い致します。
閲覧数・いいね数
閲覧数
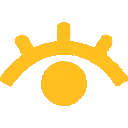
1345
いいね

3
お役立ちコンテンツ
「 集団生活」に関連する記事
2023/09/30
対象 8歳~
2023/03/26
対象 3歳~
2023/06/19
対象 6歳~
\「集団生活」に関する記事をもっと見る!/
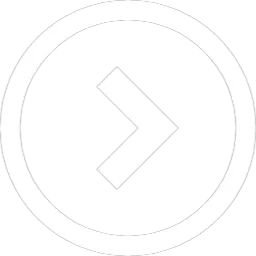
気になるテーマをすぐチェック!
児発・放デイ!施設紹介
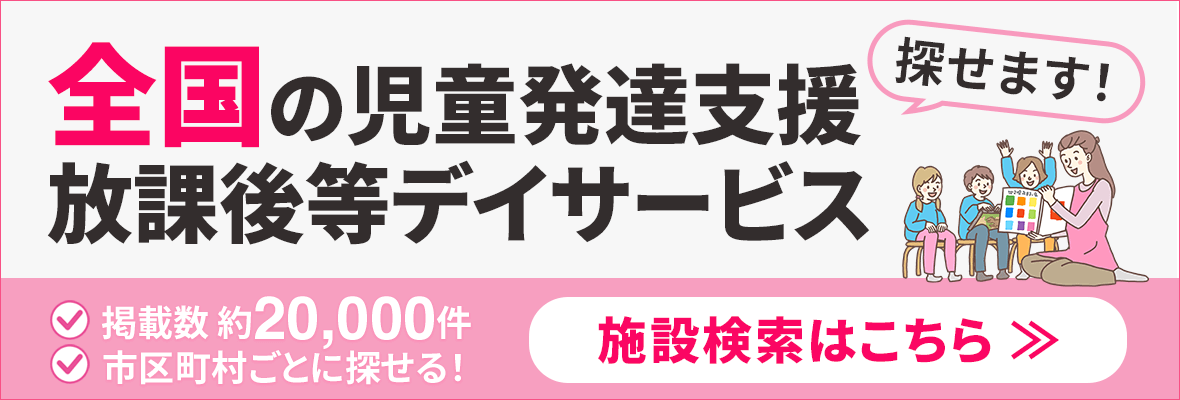



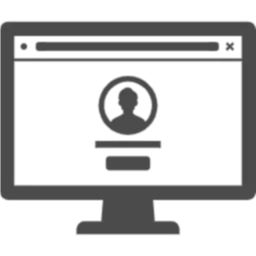


 「 集団生活」に関連する記事
「 集団生活」に関連する記事
 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!