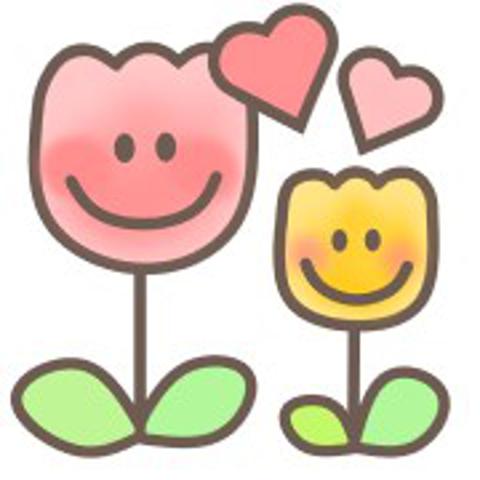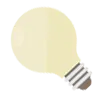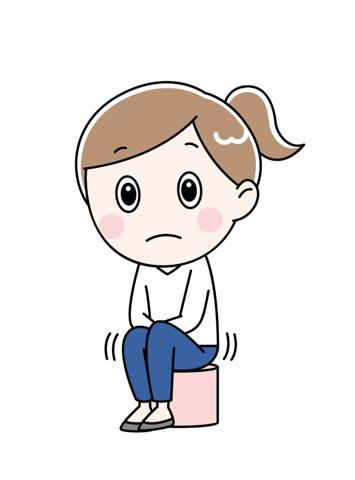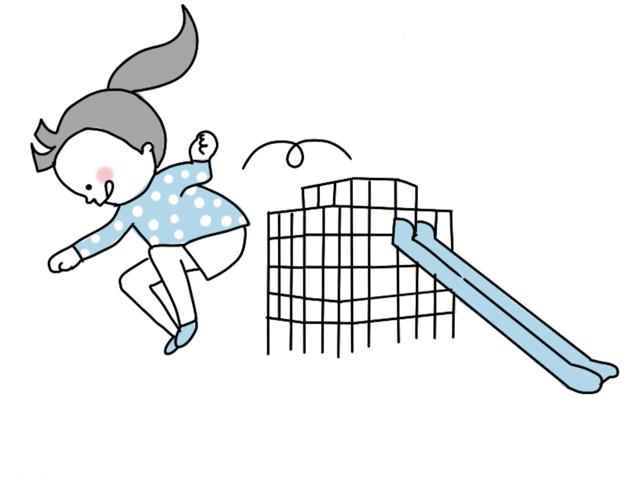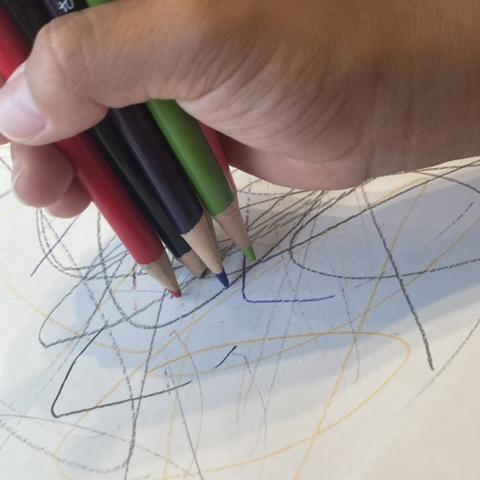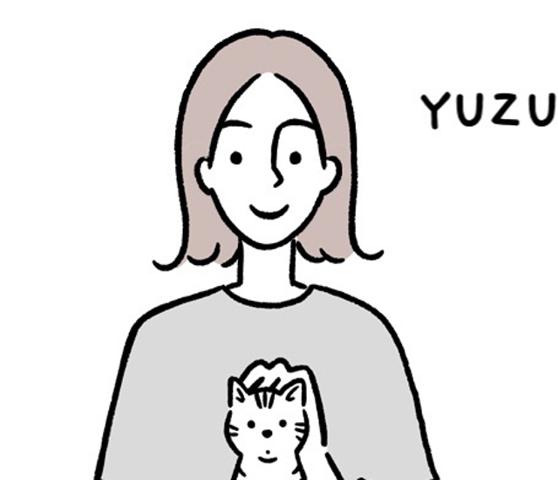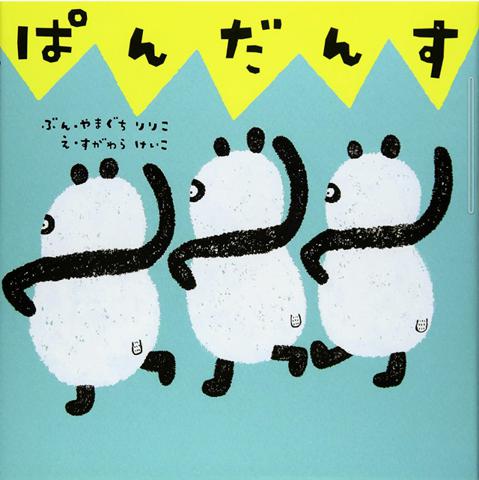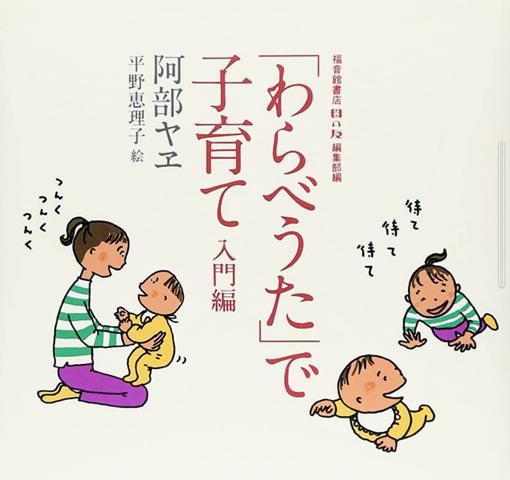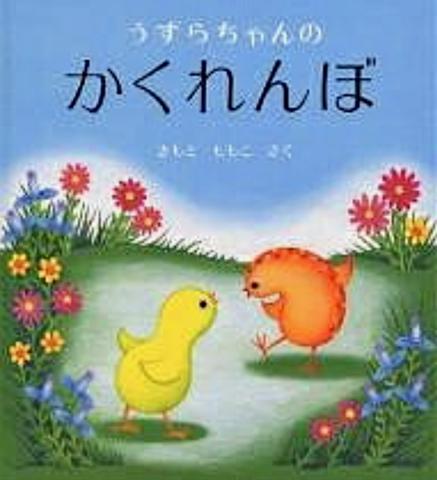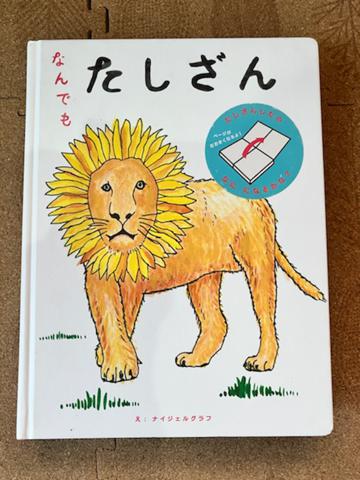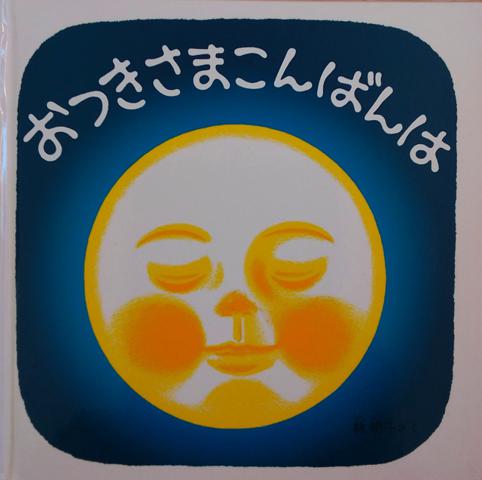| 困った時の声かけ | あそびと声かけ | 絵本と声かけ |
| 0-2歳の声かけ | 3-5歳の声かけ | 小学生の声かけ |
子どもの危険予知・察知能力が低い理由と高める方法を紹介します
記事の目次
サマリー
高いところに上ったり、とがったものを振り回したり、道路に飛び出したり…子どもは大人がヒヤッとするような危険なことをやってしまうことがありますよね。命の危険や取り返しのつかない大けがを避けるため、保護者の方は片時も目が離せず気を張っていらっしゃることでしょう。
本当に毎日お疲れ様です。
この記事では、子どもが危険予知できるようになるのは何歳ごろなのか、また、危険を回避できるトレーニングや声かけにはどのようなものがあるのか、について解説します。
記事の執筆者
危険予知・予測能力が低い背景・理由
他者の視点が未熟
子どもの認識能力は大人とは違います。
これをしたらどうなるかといった未来の予測や、相手から見たらどうかといった他者の視点で物事をとらえる力が未熟なため、大人だったらやらないことをやってしまい、危険な行動となってしまいます。
高いところから落ちるとどうなるのか、急に道路に飛び出すとどんな危険があるのか、周りに人がいるところで固いものを投げたらどうなるのか、経験のない子どもにはそれが分かりません。
行動範囲の広がり
年齢が上がり様々なことを経験するにつれて危険予知能力は発達していきますが、行動範囲もまた広がっていくため、危険の種類は変化していきます。
心理的な状態や個人差
危険予知能力には個人差もあります。
また、普段はできていても疲れや眠気などの体調や、ハイテンションや意地になっている、何かに気を取られているなどの心理的な状態によっても判断力が低下します。
環境を整えることが重要
高いところからの転落、水の事故、交通事故、誤飲、窒息、やけどなど、命を失ったり重い後遺症が残ってしまうようなことが起こらないよう、環境を整えたり大人が見守ったりすることはとても大切なことです。
危険予知能力の成長には小さいな痛みや失敗が大事!
怪我をしないようにあらゆることを「危ない!」「ダメ!」と遠ざけてしまうのも、かえって子どもの危険予知能力の発達を妨げてしまいます。
子どもは、小さな痛みや失敗を経験しながら少しずつ危険を認識していくようになるものです。
子どもの命を守りながら、安全な行動がとれるようになるため、年齢に応じたかかわり方を工夫していきましょう!
危険予知・予測能力を高めるトレーニング・声かけ

0歳児
室内での事故が多いです。
大人が必ず見守り、危険のない環境を整えます。五感を通して自分の身の回りの世界を知る時期です。
色、形、音、匂い、味、固さ、温度などを感じ取れるよう、安全を確保したうえで様々なものに触れさせてあげましょう。
赤ちゃんが感じていることを言葉にして感覚と言葉を結び付ける声かけをします。
「ふわふだね~」「あったかいね」「気持ちいいね」心地よい経験をたくさんさせてあげましょう!
1、2歳児
屋外での活動が増え、屋外での事故が多くなります。危険な行動は体で止めます。
この時期は、手を離すとボールが下に落ちる、太鼓をたたくと音が鳴る、など、自分の行動とその結果が結びつくようになっていき、繰り返し試して楽しむ時期です。
まだ自分にかかわる狭い範囲しか認識できないため、常に大人が見守り安全な環境を整えます。
歩き始めると転んでひざをすりむくなどといった経験が増えると思います。
小さな怪我や痛みを経験しながら身体の使い方も上手くなっていきます。
痛くて泣いているときに、「イタイイタイだね」「アッチッチだね」「痛かったね。転んじゃったね」「お怪我しちゃったね」「危ないね」などの声をかけて、”痛い”という感覚と「痛い」という言葉が結びつくようにしてあげましょう。
そうするとその後、「(それやると)イタイイタイだよ」「アッチッチだよ、触らないでね」「危ないよ」と声をかけることで「気を付けよう」という意識が働きやすくなります。
また、「前を向いて歩こうね」「横断歩道では1回止まって右、左、右だよ」など、場面に応じて適切な行動を教えていきましょう。
特に、命にかかわることに関しては繰り返し真剣に伝えましょう。
危険な場面ではあらかじめ伝えて気を付ける意識を持たせることが大切です。
イヤイヤもあり思うようにはいかず大変かと思いますが、根気よく繰り返すことで覚えていきます。
3~5歳児
お友達とのかかわりが増えてきます。
滑り台の上でお友達を押すと落ちてしまうから危ない、近くに人がいるところで急に動くとぶつかる、ブランコをしているそばを通ると危ない、など、日常生活の中で周りに人がいるときのふるまい方を学んでいきます。
お友達とのかかわりを通して他者の視点を学んでいくことで、自分にも相手にも安全な行動がとれるようになっていきます。
また、危険な場面の知識や経験が身についてきて、結果を予測することができるようになってくるので、危険な場面について絵を見せながら「滑り台の上で、早くしてってお友達を押したらどうなるかな?」と考えさせることも有効です。
「こういうときどうする?」「どこに気を付けたらいいかな?」と適切な行動を考えてもらうこともよいでしょう。
高いところに上りたがったり、グラグラするところにあえてチャレンジしたがったりという子もいます。
バランス感覚や力加減、重力、スピード、揺れ、傾きといった身体感覚を育てたいという欲求が出てくる時期だからです。
アスレチックやバランスボード、トランポリン、ブランコなど、身体のバランスや筋力などを使う遊びを安全に思いっきりできる環境を整えます。
とっさの時に姿勢を立て直したりすることができるようになり、けが予防になります。
また、危険なものを扱う経験をしていくことも大切です。
キャンプや料理などで火や刃物を扱うときなど、大人が見本を見せてあらかじめ注意点を伝えたうえで実際に触らせてみましょう。
本当に危険なものを慎重に扱う姿勢を身に着けていきます。
「(包丁を見せて)刃の部分を触ると手が切れてしまいます。特に先と手前のとがっているところに気を付けようね」と具体的なポイントを伝えたり、「抑える手が切れないように猫さんの手にしようね」とイメージしやすい言葉を使うことが大切です。
小学校低学年
子どもだけで行動することが増え、登下校中や帰宅後の交通事故が増えます。
救急車の呼び方、ケガの手当てなど、とっさの時の対応の仕方などを普段から伝えておきましょう。
お友達といることでハイテンションになってふざけたり気分によって周りが見えなくなってしまうことで事故が起こりやすくなります。
小学校高学年以降
知識として危険性を学ぶことで自分の行動に生かしていくことができるようになっていきます。
自転車での事故が増えるため、事故の起こりやすいパターンを予習しておきましょう。
また、物理的な事故ばかりでなく人間関係やネット上などでのトラブルが多くなってきます。
詐欺や犯罪に巻き込まれないよう、手口を親子で学んだりニュースを話題にしたりするとよいでしょう。
困ったときに相談できる親子関係を築き、一つ一つの経験から学んでいくようにしましょう。
記事の執筆者
・大学、大学院にて臨床心理学を専攻
・スクールカウンセラー、児童精神科のカウンセラー、
・発達障害児の治療教育的学習支援者として勤務
・家庭教師経験8年
【資格】
・臨床心理士
・公認心理師
・教員免許(中・高)
5児を育てながら、発達障害のあるお子さまや不登校のお子さまの学習支援、発達支援も行っています。
閲覧数・いいね数
閲覧数
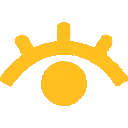
8582
いいね

6
お役立ちコンテンツ
参考・外部リンク
「 落ち着きがない」に関連する記事
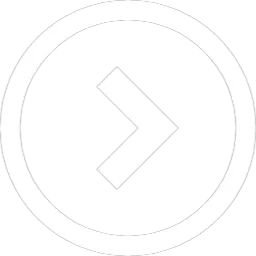
気になるテーマをすぐチェック!
- 落ち着きがない ( 80 )
- 衝動的 ( 56 )
- 危ない ( 12 )
- 危険 ( 14 )
-
危険予知 ( 1 )
Podcast「コドモトハナス」🎧✨
#2-42 無意識の防衛本能!?高学年でも甘えん坊でお使いにいけない子 2026/1/16
#2-41 ワーキングメモリのキャパオーバーを防ぐ朝の支度の習慣化 2026/1/9
#2-40 お正月に実家や親戚が集まる場所が苦手な時はどうすればいい? 2026/1/2
#2-39 その言葉はちょっと傷つくよ...。「バカ」「ヘタクソ」を言ってしまう子の背景と接し方 2025/12/26
#2-37 モヤモヤする...子ども同士のいじり・からかい 2025/12/12
#2-36 暴走する義母からのクリスマスプレゼント 2025/12/5
#2-35 どっぷり浸からず人並みには使えて欲しいデジタルデバイスについて 2025/11/28
#2-34 さほど面白くない子どもの話が延々と続いて困っています(7歳児のママ) 2025/11/21
聞いた瞬間から使えます。おすすめ!
0~2歳が夢中になる!おすすめ絵本
児発・放デイ!事業所の紹介トップ
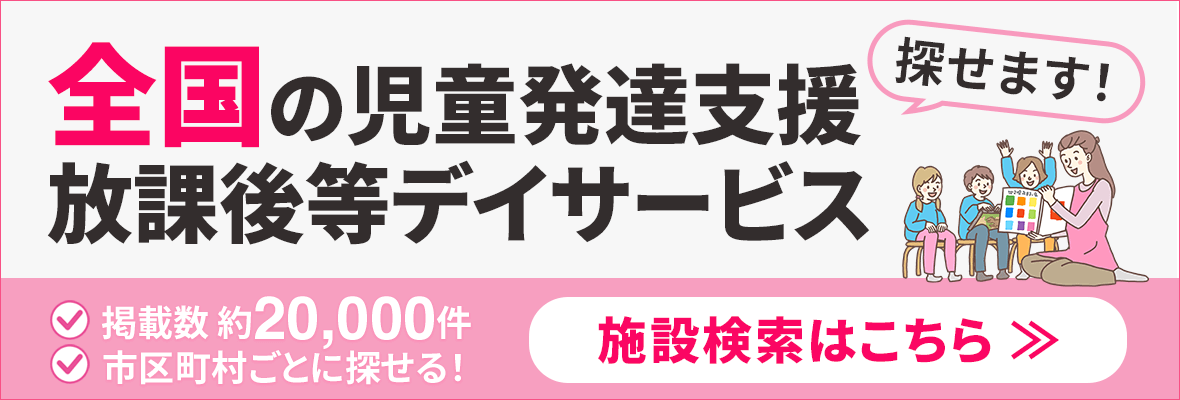




 「 落ち着きがない」に関連する記事
「 落ち着きがない」に関連する記事 気になるテーマをチェック!
気になるテーマをチェック!